DeNA東克樹投手に学ぶ!「アバウトな投球」を卒業し試合で勝てる投手になるための精密コントロール練習法
なぜ東克樹投手は打たれないのか?精密コントロールの秘密
「うちの子、ピッチャーをやりたいって言うけど、コントロールが悪くて四球ばかり…」
「どうすれば試合でストライクが入るようになるんだろう?」
野球パパなら、一度はこんな悩みにぶつかったことがあるのではないでしょうか。僕も、息子がマウンドで苦しむ姿を見るたび、野球未経験の自分には何ができるのかと、もどかしい思いをしてきました。
そんな悩める親子にとって、最高の教科書となるのが、横浜DeNAベイスターズのエース・東克樹投手です。
プロ野球選手としては小柄な身長170cmながら、彼の最大の武器は、まるでピッチングマシンのように寸分の狂いもなく投げ込まれる「精密コントロール」。トレンド情報でも、今季初の中5日という厳しい条件でリーグ最速10勝目を挙げるなど、その安定感は群を抜いています。
この記事では、なぜ東投手がこれほどまでに打者を圧倒できるのか、その秘密を徹底解剖。そして、彼の投球哲学やフォームの特徴を、私たち少年野球の親子が「明日から真似できる」具体的な練習法にまで落とし込んで、情報量盛りだくさんで解説していきます。
この記事を読み終える頃には、あなたは単なる練習方法だけでなく、お子さんのコントロールを劇的に改善するための「考え方」と「親としての最適なサポート方法」まで、すべて手に入れているはずです。
驚異的なデータが示す「無駄球ゼロ」の投球哲学
東投手の凄さを最も端的に表すのが、「BB/9」という指標です。これは、ピッチャーが9イニング投げた場合に平均でいくつフォアボール(四球)を出すかを示す数値で、低ければ低いほどコントロールが良いことを意味します。
| 年度 | 投球回 | 与四球 | BB/9 | リーグ順位 |
| 2023年 | 125.0回 | 13個 | 0.94 | 1位 |
| 2025年 | 105.1回 | 13個 | 1.11 | 2位 |
2023年には、規定投球回に達した投手で唯一1.00を下回るという、まさに「異次元」の記録を打ち立てました。「打者に無料で一塁をくれてやらない」という、彼の強い意志がこの数字に表れています。
精密コントロールを生み出す「フォームの再現性」
では、なぜ東投手はこれほど正確にボールを操れるのでしょうか。その答えは、徹底的に磨き上げられた「フォームの再現性」にあります。
- 体の開きを抑える「壁」: 東投手は、グラブを持つ左手を投げたい方向にしっかり向け、体の開きを抑える「壁」を作るのが非常に上手です。これにより、力が逃げずにボールに伝わり、コントロールが安定します。
- 常に一定のリリースポイント: 参考記事の分析にもあるように、東投手は「頭の位置」「前足の着地」「トップの高さ」が毎回ほぼ同じです。ブルペンのマウンドには、彼の踏み出した足跡が1本しか残らない、というのは有名な話。これは、寸分の狂いもなく同じ動作を繰り返せている証拠です。
彼は特別なことをしているわけではありません。投球の基本に誰よりも忠実であること。それこそが、彼の精密コントロールの源泉なのです。
なぜ少年野球ではコントロールが最重要なのか?

「もっと速い球を投げさせたい!」
野球パパなら誰もが抱く願望ですが、少し待ってください。少年野球において、チームを勝利に導くために最も重要な能力は、球速ではなく「コントロール」です。
多くの経験豊富な指導者が、「球が速いエースより、コントロールが良いエースがいた年の方が圧倒的に勝てた」と口を揃えます。
野球界には**「四死球を出すなら打たれなさい」**という有名な言葉があります。
四死球は、ヒットと同じように無条件でランナーを与えてしまうだけでなく、
- 球数が増え、ピッチャーの体力を奪う
- 守備時間が長くなり、野手の集中力が切れる
- 相手にチャンスを与え、流れを渡してしまう
といった、数多くのデメリットを生み出します。一方で、ストライクゾーンに投げて打たれることは、むしろポジティブなサイン。なぜなら、そこには「アウトを取れる可能性」が生まれるからです。
小学生のうちは、まず「ストライクゾーンに投げ込むこと」を最優先しましょう。それができれば、試合は作れます。チームは勝ちます。そして何より、ピッチャーであるお子さん自身が、野球をもっと楽しめるようになるのです。
コントロールは「技術」の前に「考え方」で劇的に変わる

さあ、いよいよ具体的な練習法の話…の前に、もう一つだけ、非常に重要なことをお伝えします。それは、コントロールは技術練習だけで身につくものではない、ということです。それを支える「考え方」を親子で共有することが、上達への一番の近道になります。
意識すべきはたった一つ、「再現性」の追求
ピッチングマシンは、なぜ常に同じ場所にボールを投げられるのでしょうか?それは、機械だからです。完全に固定され、毎回同じ動きをするからです。
コントロールが良いピッチャーとは、この**「マシンのような再現性」**を、人間の体で実現しているピッチャーのことです。
ボールをコントロールする前に、まず**「自分の体をコントロールする」**。この意識がお子さんの中に芽生えた時、ピッチングは劇的に変わります。片足で立つ、腕を振る、踏み込む。この一連の動作を、毎回寸分の狂いなく再現することを目指すのです。
親ができる最高のサポートは「良いイメージの記憶」
ここで親の出番です。お子さんが良いボールを投げた時、あなたは何と声をかけますか?
「ナイスボール!」
もちろん、それも素晴らしい声かけです。でも、もう一歩踏み込んでみましょう。
「今投げた時のフォーム、すごく安定してたね!頭が全然ブレてなかったよ!」
このように、良かった時の「フォーム」や「体の感覚」を具体的に褒めてあげるのです。すると、子供の脳には「良い投球のイメージ」が強く記憶されます。悪い点を指摘するのではなく、良かった点を具体的に褒めて記憶させる。これこそが、親ができる最高のメンタルサポートです。
「コース」と「高低」は手先で操作しない
小学生がコースを狙おうとすると、どうしても手先でボールを操作しようとしてフォームを崩しがちです。
- コースは「立ち位置」で調整する: ボーリングで立ち位置を変えるように、ピッチャーもプレートを踏む位置でコースを調整します。右バッターのインコースを狙うならプレートの右端を踏む、というように、体ごと狙う方向に向けるのです。
- 高低は「歩幅」で調整する: 低めに投げたい時は、踏み出す足の歩幅をほんの少し広くする。高めにしたい時は、ほんの少し狭くする。この微妙な感覚を、投げ込みの中で体に覚えさせていきます。
手先ではなく、全身でコントロールする感覚を養うことが大切です。
明日から親子で始める!コントロール向上ドリル【3つのフェーズ】
お待たせしました!ここからは、東克樹投手の考え方をベースに、少年野球の選手が明日からすぐに実践できる具体的なコントロール向上ドリルを、3つの段階(フェーズ)に分けてご紹介します。
フェーズ1:フォームの土台作り【再現性を高める】
まずは、安定したコントロールの源泉となる「フォームの再現性」を高めるための基礎練習です。
練習①:シャドーピッチング(足跡印つき)
タオルなどを持って、鏡や窓に映る自分を見ながらフォームを確認する、おなじみの練習です。ここに一工夫。ストライクが入った時の「踏み出した足の位置」にテープなどで印をつけ、毎回必ず同じ場所を踏むように意識させましょう。東投手の「ブルペンの足跡は1本」を親子で目指すのです。
練習②:片足立ち静止スロー
投球動作の始動を安定させるためのドリルです。軸足1本で立った状態で、3~5秒間ピタッと完全に静止してから投げます。グラグラするお子さんは多いですが、この「静止」ができるようになると、投球フォームが一気に安定します。毎日10回でもいいので、継続することが重要です。
練習③:下半身の安定化(元阪神・秋山拓巳氏の提言)
2017年に12球団で最も四球が少なかった元阪神の秋山拓巳氏は、**「軸足のかかとを動かさないこと」**の重要性を説いています。かかとがグラつくと、上半身の動きも全てズレてしまいます。軸足を地面にしっかり固定し、常に同じ場所へ真っすぐ踏み出す。マウンドに線を引いて、踏み出す足が左右にズレていないかチェックするのも非常に有効です。
フェーズ2:距離感と力加減を養う【感覚を磨く】
フォームの土台がある程度できたら、次は目標までの距離を正確に把握し、適切な力加減で投げる「感覚」を養います。
練習①:パラボリックスロー(筑波大・川村准教授の理論)
5m~10mほど離れた場所にカゴやバケツを置き、そこにボールを山なり(放物線)に投げ入れる練習です。これは筑波大学の川村卓准教授が提唱する方法で、バスケットボールのフリースロー研究からヒントを得ています。ボールが目標に届くまでの「奥行き感覚」を鍛えることで、コントロールが向上することが科学的に証明されています。入るか入らないかよりも、「きれいな放物線を描くこと」を意識して、遊び感覚で取り組んでみてください。
練習②:距離を変えたピッチング
まずは5m程度の至近距離から始め、「絶対にストライクが取れる」という自信をつけさせます。そこから2mずつ距離を伸ばしていき、どの距離でフォームが崩れたり、力みが出たりするのかを親子で分析します。
逆に、正規の距離(小学生なら16m)より長い18mや20mで投げる練習も効果的です。遠投することで、自然と体全体を使ったフォームが身につき、正規の距離に戻った時に、楽にコントロールできるようになります。
フェーズ3:実戦的な制球力を磨く【自信をつける】
最後は、試合で本当に使える「精密なコントロール」と「絶対的な自信」を身につけるための、より高度な練習です。
練習①:6割ピッチング(元オリックス・前田祐二氏の提言)
元オリックス投手の前田祐二氏が推奨する練習法です。これは、**「フォームは100%の時と同じまま、力感だけを6割に抑えて投げる」**というもの。ただ力を抜いて置きにいくボールとは全く違います。全力投球と同じフォームで、リラックスして投げる感覚を身につけることで、力みが取れ、フォームが固まります。
練習②:レベル別ストライク練習
上記の「6割ピッチング」を前提に、以下のレベルを順番にクリアしていくゲーム形式のドリルです。一つのレベルをクリアするまで次に進まない、というのがミソです。
- Level 1: 10球中8球以上ストライク(コースはどこでもOK)
- Level 2: 10球中8球以上インコース(右バッターの内側)にストライク
- Level 3: 10球中8球以上アウトコース(右バッターの外側)にストライク
- Level 4: インコースとアウトコースを交互に投げ、10球中8球以上ストライク
- Level 5: もし変化球があれば、そのボールで10球中8球以上ストライク
この練習を1ヶ月続ければ、「いつでもストライクが取れる」という絶対的な自信が芽生え、試合のマウンドでも冷静でいられるようになります。
投球の土台を作る!自宅でできる体幹・バランストレーニング

良いフォームで投げるためには、それを支える強靭な体幹とバランス能力が不可欠です。専門的な器具がなくても、自宅で簡単にできるトレーニングを紹介します。
- ビームウォーク: 水を入れたペットボトルやバッグを頭の上に乗せ、バランスを取りながら平均台のような細い板の上を歩きます。体幹、特に体の軸をまっすぐに保つ感覚を養うのに最適です。
- ローリング片手プッシュアップ: 仰向けに寝転がった状態から回転し、片手の腕立て伏せで起き上がります。体の連動性とバランス感覚を同時に鍛えることができる優れたトレーニングです。
これらの地味な練習が、マウンド上での安定感に直結します。
親子で取り組む最強のサポート体制とは?
ここまで技術的な話をしてきましたが、子供の成長には、何よりも親のサポートが不可欠です。しかし、間違ったサポートは逆効果にもなりかねません。ここでは、野球パパが実践すべき「最強のサポート術」をお伝えします。
結果よりプロセスを褒める「ポジティブ声かけ術」
前述の通り、親の役割は技術指導者になることではありません。子供の一番の理解者であり、モチベーターであることです。
「今日の試合、3つもフォアボールを出したじゃないか!」
これは最悪の声かけです。子供は誰よりも自分の結果を分かっています。
そうではなく、結果の裏にある「プロセス」に目を向けてあげましょう。
「フォアボールは出しちゃったけど、ピンチの場面でしっかり腕を振って投げられていたのは、すごく良かったよ!練習の成果が出てるね!」
このように、挑戦した姿勢や、練習してきたことが少しでも出せた部分を具体的に見つけて褒めてあげるのです。この一言が、子供の「次も頑張ろう」という意欲を引き出します。
子供の体を守る!怪我予防への正しい知識
熱心なあまり、練習のさせすぎで子供を故障させてしまうのは、最も避けなければならないことです。特に成長期の子供の肩や肘は非常にデリケート。**「投げすぎによる故障は、100%大人の責任」**ということを肝に銘じてください。
近年、プロ野球選手でも「トミー・ジョン手術」という肘の靭帯再建手術を受ける選手が増えています。これは、少年時代の投げすぎが原因の一つとも言われています。
量をこなすことよりも、一球一球を意識した質の高い練習を心がけましょう。そして、練習後には必ずストレッチを行い、体のケアをする習慣をつけさせてください。お子さんの野球人生を長く、豊かなものにするために、目先の勝利よりも将来を見据えたサポートをお願いします。
まとめ:東克樹投手に学び、「アバウトな投球」を卒業しよう
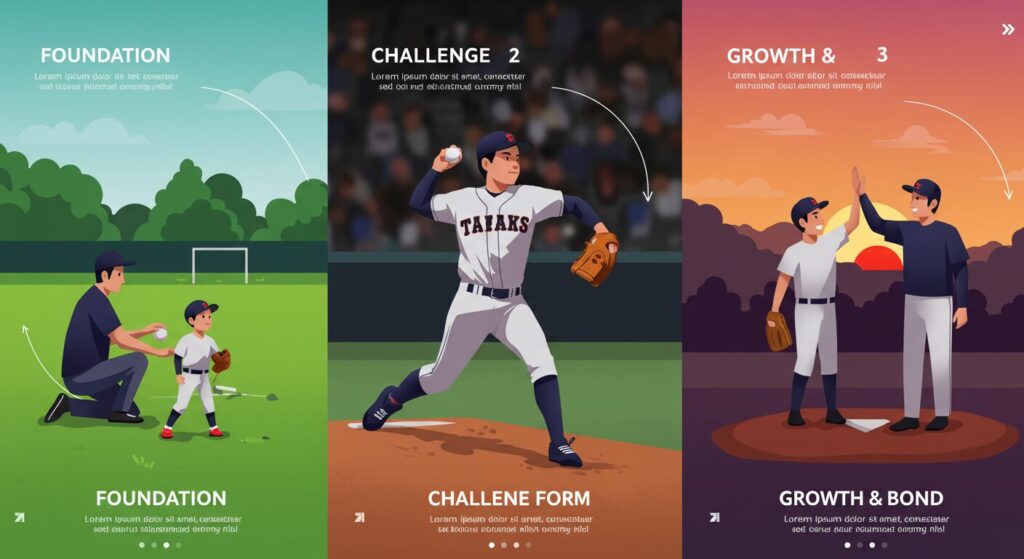
最後に、この記事でお伝えした最も重要なポイントをまとめます。
- 目指すべきは東克樹投手のような「精密コントロール」: 彼の強みは、徹底的に磨かれた「フォームの再現性」から生まれる。
- 少年野球は「コントロール」が最重要: 四死球による自滅を防ぎ、試合を作れるピッチャーがチームを勝利に導く。
- 上達の鍵は「考え方」: 「自分の体をコントロールする」という意識を持ち、手先ではなく全身で投げる感覚を養う。
- 練習は3つのフェーズで段階的に: 「土台作り」→「感覚養成」→「実戦力強化」と、焦らず一歩ずつ進めることが大切。
- 親の役割は最強のサポーター: 技術的なダメ出しは指導者に任せ、親はプロセスを褒めて自信を育み、怪我から守ることに徹する。
コントロールの悩みは、一朝一夕には解決しないかもしれません。しかし、今日ご紹介した「考え方」と「練習法」を親子で共有し、コツコツと継続していけば、必ず道は開けます。
アバウトな投球にさよならして、マウンドで自信に満ち溢れた表情で投げるお子さんの姿を、一緒に目指していきましょう!

