【中学野球】部活廃止?「地域移行」の全貌と費用・指導者のリアル|NPB栗山英樹氏の支援と海外事例に学ぶ未来
「ねえパパ、中学に入ったら野球部がないかもしれないって本当?」
先日、小学6年生になる息子が、練習帰りの車の中で不安そうに聞いてきました。
「え? まさか。中学校には野球部があるのが当たり前だろう?」
私はとっさにそう答えましたが、胸の中には以前ニュースで見かけた「部活動の地域移行」という言葉が引っかかっていました。
家に帰って調べてみると、驚愕の事実が。
「公立中学校の部活動を、地域のクラブチームなどに移行する」
そんな改革が、まさに今、私たちの足元で進行していたのです。
「部活がなくなる? じゃあ、どこで野球をやればいいの?」
「月謝が高くなるって本当?」
「誰が教えてくれるの? 怖いコーチだったらどうしよう……」
私と同じように、野球未経験のパパ・ママにとって、この「地域移行」は未知の領域であり、不安の種以外の何物でもないかもしれません。しかし、情報を深掘りしていくうちに、私は一つの希望を見つけました。
それは、「これは『部活の崩壊』ではなく、世界標準のクラブチーム化への『進化』である」という視点です。
これまで私たちは、「学校に入れば自動的に部活がある」という環境に甘えていたのかもしれません。しかしこれからは、私たち親が子供の性格やレベル、そして家庭の事情に合わせて「最適な環境を自ら選ぶ」プロデューサーになる必要があります。
この記事では、野球未経験のパパである私が、徹底的なリサーチと取材(という名の先輩パパへの聞き込み)で集めた情報を元に、以下のことを全力で解説します。
- 地域移行の「いつから?」「どうなる?」の全貌
- アメリカやドミニカなど「世界の野球育成」から見る日本の未来
- 指導者・費用・送迎……親が直面する「3大不安」のリアルと対策
- 救世主となるか? NPB(プロ野球)と栗山英樹氏の新たな支援プロジェクト
- 失敗しないための「チーム選び」チェックリスト
現在2025年11月。改革推進期間の佳境を迎えた今だからこそ分かる「リアル」な情報をお届けします。
この記事を読めば、漠然とした不安が消え、お子さんと一緒にワクワクしながら次のステージを選べるようになるはずです。さあ、一緒に未来の野球界の扉を開けましょう!
そもそも「部活動の地域移行」とは? 親が知っておくべき基礎知識
まずは、敵(といっては失礼ですが)を知ることから始めましょう。「部活動の地域移行」。言葉は聞いたことがあっても、具体的に何がどう変わるのか、正しく理解できている人は意外と少ないのではないでしょうか。
制度改革の背景:なぜ今「部活」が変わるのか?
「昔は放課後、暗くなるまで校庭で白球を追いかけたもんだ……」
そんな昭和・平成のノスタルジーは、令和の教育現場では通用しなくなっています。なぜ、国を挙げてこの改革が進められているのでしょうか。理由は大きく2つあります。
教員の働き方改革と少子化による廃部の危機
一つ目は、先生たちの限界です。
これまでの中学部活動は、教員の献身的なボランティア精神(顧問活動)によって支えられてきました。しかし、平日の授業に加え、土日の練習試合や大会引率……。先生たちの長時間労働は限界を超え、本来の業務である授業準備や生徒指導に支障をきたすケースも少なくありません。「野球経験のない先生がルールブック片手に顧問をする」という負担も、長年の課題でした。
二つ目は、少子化による「野球部消滅」の危機です。
生徒数が減り、単独の学校ではチームが組めない(9人揃わない)中学校が激増しています。これまでは近隣校との「合同チーム」で凌いできましたが、それも限界が見え始めています。「野球をやりたくても、学校に野球部がない」という事態が、地方だけでなく都市部でも起きているのです。
このままでは、子供たちがスポーツに親しむ機会そのものが失われてしまう。だからこそ、「学校単位」から「地域単位」へ活動の場を移し、持続可能なスポーツ環境を作ろうというのが、この改革の根本的な目的です。
「学校単位」から「地域単位」へのパラダイムシフト
これまでの「○○中学校 野球部」という看板が、「○○地域ベースボールクラブ」といった形に変わります。
学校の枠を超えて、近隣の生徒が集まり、地域の指導者や民間クラブが運営するチームで活動する。これにより、部員不足の解消や、専門的な指導を受けられる機会の増加が期待されています。
つまり、「学校教育の一環」だった部活動が、「地域社会での社会教育・スポーツ活動」へと性質を変える、歴史的なパラダイムシフトなのです。
スケジュールと現状:いつから完全移行するのか
「で、いつから変わるの?」というのが、私たち親の一番の関心事ですよね。
改革推進期間(2023~2025年度)と実行期間(2026年度~)
スポーツ庁のガイドラインによると、2023年度から2025年度までの3年間を「改革推進期間」と位置づけていました。
今は2025年11月ですから、まさにこの「推進期間」の最終盤です。この3年間で、全国の自治体でモデル事業が行われ、課題の洗い出しや受け皿作りが進められてきました。
そして、来たる2026年度からは、いよいよ全国的な「実行期間」に入ると見られています(※自治体により名称や区分は異なりますが、本格移行のフェーズです)。現在小学6年生の息子が中学に入学するタイミングは、まさにこの「本格移行元年」に当たるわけです。
「休日のみ」から「平日も」へ段階的移行のロードマップ
移行はいきなり「明日から全部地域クラブね!」となるわけではありません。
まずは「休日の部活動」から段階的に地域へ移行することが推奨されています。
- ステップ1: 土日の練習や試合を、地域のスポーツ団体や民間クラブに委ねる。
- ステップ2: 平日の放課後活動も徐々に地域へ移行する。
多くの自治体では、まずステップ1の「休日の地域移行」が進んでいます。平日は学校の先生が見て、休日は地域のコーチが見る、というハイブリッド型から始まっているケースが多いようです。
自治体による進捗のバラつきと「格差」の懸念
ここで注意が必要なのは、「住んでいる地域によって進み具合が全く違う」という点です。
ある市では既にすべての中学校で休日の部活が廃止され、地域クラブに完全移行している一方で、隣の町では「まだ検討中」で従来通りの部活が続いている……なんてことがザラにあります。
「東京の従兄弟はクラブチームに入ったけど、うちはまだ学校の部活しかない」
そんな情報格差が親たちを混乱させています。まずは自分の住む自治体の教育委員会や中学校がどのようなロードマップを描いているか、広報誌やホームページで確認することが第一歩です。
受け皿となる「地域クラブ」とは具体的に何か
「地域クラブ」と言われても、ピンときませんよね。具体的には以下の3つのパターンが想定されています。
総合型地域スポーツクラブ、民間企業、保護者会の3パターン
- 総合型地域スポーツクラブ:
地域住民が主体となって運営するスポーツクラブ。サッカーやテニスなど多種目を扱っていることが多く、その中に「野球部門」が新設されるパターン。行政からの補助金などで運営され、比較的会費が安価な傾向があります。 - 民間企業(スポーツスクール等):
フィットネスクラブやスポーツ用品店などが運営するスクール。プロのコーチが指導するため質は高いですが、その分、月謝は高額になりがちです。 - 保護者会・スポーツ少年団の延長:
既存のスポーツ少年団が中学生部門を作ったり、廃部になった部活の保護者たちが主体となって任意団体を立ち上げたりするパターン。指導者はボランティアのパパコーチやOBが中心となることが多いです。
硬式クラブチーム(シニア・ボーイズ)との住み分け
ここで忘れてはいけないのが、以前から存在する「リトルシニア」や「ボーイズリーグ」といった硬式野球クラブチームの存在です。
これらは元々、学校の部活とは別に活動していた「ガチ勢」向けのチームでした。
地域移行が進む中で、
- 「競技志向(ガチ)」なら硬式クラブチームへ
- 「エンジョイ志向・育成志向」なら新設される軟式の地域クラブへ
というような住み分けが進むと考えられます。
しかし、地域によっては軟式の地域クラブが強豪化したり、逆に硬式チームが敷居を下げたりと、境界線が曖昧になっているケースもあります。「硬式か軟式か」という選択肢に加え、「どの運営主体のチームに入るか」という選択肢が増えたことになります。
スポーツ庁|学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン
日本の「部活」は特殊? 世界の中学年代(U-15)野球事情【海外事例】
「部活がなくなるなんて、日本の野球は終わりだ!」
そんな悲観的な声も聞かれますが、ちょっと視点を広げてみましょう。実は、「学校の中に運動部があって、教師が指導する」という日本のシステムは、世界的に見るとかなり特殊なんです。
世界では、13歳~15歳の子供たちはどのように野球をしているのでしょうか。海外の事例を知ることで、地域移行がもたらす「新しい可能性」が見えてくるかもしれません。
アメリカ型:シーズン制と「トラベルボール」
野球の母国アメリカ。ここでは「部活」という概念はありません。
学校部活と地域クラブ(トラベルボール)の共存関係
アメリカの中学校(Middle School)や高校にも野球チームはありますが、活動期間が限られています。
その隙間や並行して活動するのが、地域のレクリエーションリーグや、よりレベルの高い「トラベルボール(Travel Ball)」と呼ばれるクラブチームです。トラベルボールはその名の通り、州をまたいで遠征し、トーナメントを戦う選抜チーム。日本の「シニア」や「ボーイズ」に近いイメージですが、より流動的で、複数のチームを掛け持ちすることもあります。
季節ごとに競技を変える「シーズン制」のメリット・デメリット
アメリカの最大の特徴は「シーズン制」です。
- 春~夏:野球
- 秋:アメリカンフットボールやサッカー
- 冬:バスケットボールやアイスホッケー
このように、季節によって異なるスポーツに取り組むのが一般的です。これにより、特定の筋肉への過度な負担(投げすぎなど)を防ぎ、運動能力を多角的に伸ばすことができます。大谷翔平選手のようなスーパーアスリートが生まれる土壌は、この「マルチスポーツ」にあるとも言われています。
高額化する費用とトライアウトによる選抜の厳しさ
一方で、アメリカ型にも課題はあります。特にトラベルボールは、遠征費や参加費が非常に高額で、「Pay to Play(プレーするためにお金を払う)」の格差が社会問題になっています。裕福な家庭の子しか高いレベルで野球ができない、という現実があるのです。また、チームに入るためのトライアウト(選抜試験)も厳しく、実力がなければプレーする場所すら確保できないというシビアさもあります。
ドミニカ共和国型:MLBを目指す「アカデミー」システム

多くのメジャーリーガーを輩出するドミニカ共和国。ここのシステムは、日本の部活とは対極にあります。
学校教育とは切り離された「プロ養成所」としての機能
ドミニカでは、10代前半から「アカデミー」と呼ばれる施設に入り、野球漬けの日々を送る子供たちがいます。これは学校教育とは完全に切り離された、いわば「プロ養成所」。MLB球団が直接運営するものや、民間の「ブスコン(Buscones)」と呼ばれる代理人が運営するものがあります。
貧困脱出の手段としての野球と「ブスコン(代理人)」の存在
彼らにとって野球は、遊びや教育ではなく、「貧困から脱出し、家族を養うための手段」です。そのため、ハングリー精神は凄まじいものがあります。ブスコンは才能ある子供を見つけ、食事や用具を提供して育て上げ、契約金の一部を受け取るビジネスモデルで成り立っています。
「勝利」よりも「個の能力(将来性)」を最優先する育成哲学
ここでは、チームの勝利よりも「個人の能力をどう伸ばすか」が最優先されます。目先の大会で勝つことよりも、16歳でMLBと契約するために必要な球速やパワー、身体能力を磨くことに特化しています。バント練習などはほとんどせず、とにかく「遠くへ飛ばす」「速く投げる」ことが評価されるのです。
ドイツ型:地域コミュニティの核「総合型スポーツクラブ」
サッカー強豪国のドイツですが、スポーツ環境のシステムは野球にも応用できるヒントがあります。
学校に部活がない社会:放課後は地域の「フェライン」へ
ドイツには学校部活が基本的にありません。子供たちは放課後、地域にある「フェライン(Verein)」と呼ばれる総合型スポーツクラブに行きます。ここには老若男女が集まり、サッカー、体操、テニスなど様々なスポーツを楽しんでいます。
多世代・多種目が共存するコミュニティ重視の運営
フェラインの特徴は、「地域コミュニティ」としての機能です。
エリートを目指すコースもあれば、週1回楽しく汗を流すコースもある。子供からお年寄りまでが同じクラブの会員として交流し、地域の大人たちが指導者や運営スタッフとしてボランティアで関わります。日本の「地域移行」が理想とするモデルの一つが、このドイツ型と言えるでしょう。
ボランティア指導の限界とプロ化への過渡期
ただ、ドイツでも近年は指導者のなり手不足や、専門性の向上が課題となっており、有償のプロコーチを雇うクラブが増えています。ボランティア依存からの脱却は、日本と同様の課題と言えます。
海外事例から見る日本の「地域移行」の可能性
日本が目指すのは「ドイツ型」コミュニティと「米国型」競技性のハイブリッドか
こうして見ると、日本の部活は「学校教育」と「競技スポーツ」を一身に背負いすぎていたのかもしれません。
地域移行によって、日本の中学野球は、
- ドイツ型のような「地域の受け皿(誰もが楽しめる場所)」
- アメリカやドミニカ型のような「専門的な育成の場(上を目指す場所)」
この2つに分化し、それぞれのニーズに合わせて選択できるようになる可能性があります。
「部活がなくなる」と嘆くのではなく、「子供の目的に合った環境を選べるようになる」と捉えれば、この変化はチャンスにもなり得ます。
親の3大不安「指導者」「費用」「場所」のリアルと対策
世界の話も参考になりますが、やっぱり気になるのは「明日の我が子」のこと。
地域移行に伴って親たちが抱える3つの大きな不安、「指導者」「費用」「場所」について、現状のリアルと私たちができる対策を掘り下げていきましょう。
誰が教えるのか? 指導者の「質」と「資格」問題
「近所の野球好きのおじさんが、ボランティアで教えることになるの?」
「昔ながらの怒鳴り散らすコーチだったらどうしよう……」
指導者の質は、子供の成長だけでなく、野球を好きでい続けられるかを左右する最重要項目です。
兼業教師、地域ボランティア、有償コーチの混在
移行期である現在は、様々な立場の指導者が混在しています。
- 兼業教師: 平日は教師として働き、土日は「副業(兼職兼業)」として地域クラブのコーチをする先生。これまでの部活顧問がそのまま移行する形ですが、報酬が発生する点で責任の所在が変わります。
- 地域ボランティア: 地元の野球経験者や保護者コーチ。情熱はありますが、指導スキルのバラつきや、古い指導法(長時間練習、根性論)からの脱却が課題となることも。
- 有償コーチ: 民間クラブなどで雇用されるプロの指導者。技術指導の質は保証されますが、その分、会費に反映されます。
JSPO公認スポーツ指導者資格とは? 親がチェックすべきポイント
指導者の質を見極める一つの基準として、「JSPO(日本スポーツ協会)公認スポーツ指導者資格」があります。
特に「軟式野球コーチ1」「スタートコーチ」などの資格は、技術だけでなく、発育発達や安全管理、コンプライアンスについての講習を受けている証明になります。
チーム選びの際は、「コーチは何か資格を持っていますか?」「指導者講習会には参加されていますか?」と聞いてみるのも勇気ある一歩です。まともなチームなら、胸を張って答えてくれるはずです。
「暴言・ハラスメント」を防ぐためのガバナンスと通報窓口
地域移行で最も懸念されるのが、学校という「目」が届かなくなることによるハラスメントの温床化です。
これに対抗するには、「組織のガバナンス(統治)」が機能しているかを確認する必要があります。
- 保護者の当番制で常に大人の目があるか?(監視の意味で)
- クラブ内に相談窓口や、匿名で意見を言える仕組みがあるか?
- 全日本軟式野球連盟(JSBB)の「学童・少年野球の指導指針」を遵守しているか?
これらが整備されているクラブは、健全な運営をしている可能性が高いです。
お金はいくらかかる? 部活無料神話の崩壊と受益者負担
「部活なら月数千円の部費で済んだのに……」
正直、ここが一番痛いところかもしれません。地域移行は「受益者負担」、つまりサービスを受ける人が対価を払うのが原則になります。
年会費、月謝、遠征費、保険料…費用の内訳シミュレーション
地域クラブに移行した場合の費用感(目安)をシミュレーションしてみましょう。
- 入会金・年会費: 5,000円~10,000円(年)
- 月謝(会費): 3,000円~10,000円(月)
- ボランティア中心なら安く、プロコーチなら高くなります。
- スポーツ保険: 800円~2,000円(年)
- ユニフォーム・道具代: 30,000円~50,000円(初期)
- 学校指定のジャージではなく、チーム専用ユニフォームを購入する必要があります。
- 遠征費・合宿費: 実費(数千円~数万円)
部活時代は年間数千円~1万円程度だった負担が、年間5万~10万円以上になることも珍しくありません。
「月謝が高い」=「悪」ではない? サービス対価としての指導
「高い!」と反射的に思ってしまいますが、考え方を変えれば「対価を払って正当なサービス(指導)を受ける」ということでもあります。
無料(ボランティア)だからこそ、「指導法に口が出せない」「お茶当番などの労力奉仕を強いられる」という側面もありました。お金を払うことで、「質の高い指導」「保護者負担の軽減(当番なし)」が得られるなら、それは「投資」として合理的かもしれません。
低所得世帯への支援策(就学援助制度の活用など)
「経済的に苦しい家庭は野球ができなくなるのでは?」という懸念に対しては、行政も対策を始めています。
一部の自治体では、「就学援助制度」の対象に地域クラブ活動費を含めたり、「スポーツバウチャー(クーポン)」を配布して会費の一部を助成したりする取り組みが始まっています。あきらめる前に、役所の窓口や学校に相談してみることを強くお勧めします。
どこでやるのか? 練習場所の確保と送迎の負担
「学校のグラウンドが使えないなら、どこに行くの?」
場所と移動の問題も切実です。
学校グラウンドの開放ルールとナイター設備の有無
基本的には、休日の中学校のグラウンドや体育館を地域クラブに開放する方向で調整が進んでいます。しかし、全てのクラブが希望通りに使えるわけではありません。
また、平日の夜間練習を行う場合、中学校にはナイター設備がないことが多いため、市営球場や民間の練習場を借りる必要が出てきます。これが費用増の原因にもなります。
「送迎問題」が親の負担増に? チームバスや乗り合いの現実
練習場所が遠方になったり、夜間練習が増えたりすると、親の送迎が必須になります。
「毎週末、車出し係をするのは無理……」
そんな親の悲鳴に応えるため、チームバスを保有するクラブや、地域の巡回バスを活用する事例も出てきています。また、保護者同士で「乗り合い(カープール)」のルールを決めて負担を分散する工夫も必要になるでしょう。
救世主となるか? NPBと栗山英樹氏の「中学球児応援プロジェクト」

不安ばかり並べてしまいましたが、ここで明るいニュースを。
日本の野球界の頂点であるNPB(日本野球機構)が、この中学野球の危機に対して本気で動き出しています。
プロジェクト発足の経緯と狙い
「日本野球のベースは中学野球」栗山英樹・斎藤佑樹アンバサダーの想い
2024年、NPBは「中学球児応援プロジェクト」を発足させました。
アンバサダーに就任したのは、WBC優勝監督の栗山英樹氏と、元プロ野球選手の斎藤佑樹氏。
栗山氏は会見でこう熱く語りました。
「日本野球のベースを作っているのは中学野球。ここがしっかりしないと、日本の野球は終わる」
この言葉には、単なる人気取りではない、現場への強い危機感と愛が込められています。
競技人口減少と「野球離れ」への危機感
高校野球の競技人口が減少を続ける中、その供給源である中学野球の環境悪化は、プロ野球にとっても死活問題です。地域移行による混乱で「野球をやめてしまう子」を出さないために、プロ野球界がその資金力と発信力を使って支援に乗り出したのです。
具体的な支援内容:プロのノウハウを地域へ
では、具体的に何をしてくれるのでしょうか?
全国47都道府県「全日本野球サミット」による連携強化
NPBは、プロ・アマの垣根を越えて、全国47都道府県で「全日本野球サミット」を開催しています。
これまでバラバラだった「中体連(部活)」「シニア」「ボーイズ」「軟式連盟」などの指導者が一堂に会し、地域の課題や解決策を話し合う場を作っています。大人が手を組まなければ、子供たちの環境は守れないからです。
指導者不足を解消する「中学野球クリニック」の開催
「誰が教えるの?」という不安に対しては、元プロ野球選手を講師として派遣する「中学野球クリニック」を展開しています。
技術指導だけでなく、指導者講習会もセットで行い、地域の指導者(お父さんコーチや教員)のスキルアップをサポート。正しい知識を持った大人が地域に増えることで、指導の質を底上げしようという試みです。
NPBジュニアトーナメントとの連携強化
これまでは小学生(12球団ジュニア)が中心だったNPBの育成活動を、中学生世代にも広げていく構想もあります。地域クラブの大会をNPBが後援したり、プロの球場を使って試合をする機会を増やしたりと、子供たちが「目標」を持てるようなイベントが増えていくでしょう。
私たち保護者はこのプロジェクトをどう活用すべきか
公式サイトやSNSでの情報収集術
このプロジェクトの情報は、NPBの公式サイトやSNSで発信されています。「うちの県でサミットやクリニックがある!」という情報をいち早くキャッチし、チームで共有したり、子供に参加を勧めたりすることで、一流の空気に触れるチャンスを作ることができます。
地域イベントへの積極参加と「声」を届ける重要性
また、こうしたイベントに参加した際は、ぜひ現場の悩み(練習場所がない、費用が高いなど)をアンケートなどで伝えてください。NPBも現場の声を欲しています。私たち親の声が、プロ野球界を動かし、地域の環境を良くするきっかけになるかもしれません。
激変期を乗り越える! 野球未経験パパ・ママのための「チーム選び」チェックリスト
制度も環境も変わる中で、最終的にチームを選ぶのは、子供と私たち親です。
「入ってみたら想像と違った……」というミスマッチを防ぐために、説明会や体験会で確認すべきポイントをまとめました。
説明会・体験会で必ず聞くべき5つの質問
以下の5つは、入団前に必ずクリアにしておきたいポイントです。遠慮せずに聞いてみましょう。
①指導方針(勝利至上主義か育成重視か)
「試合に勝つことを最優先しますか? それとも、高校野球につながる基礎や、全員の出場機会を重視しますか?」
どちらが良い悪いではなく、子供のモチベーションと合っているかが重要です。
②費用の総額と支払い方法(追加徴収の有無)
「月謝以外に、合宿費や遠征費、ウェア代などで年間いくらくらいかかりますか? 急な追加徴収はありますか?」
パンフレットに載っていない「隠れ費用」を確認しましょう。
③保護者の当番・送迎の頻度と強制力
「お茶当番や車出しはありますか? 共働きで参加が難しい場合、どうすればいいですか?」
ここが曖昧だと、後々トラブルの元になります。「できる人がやる」のか「当番制で強制」のかを確認。
④指導者の資格保有状況と更新頻度
「コーチの皆さんは、公認指導者資格をお持ちですか? 暴力や暴言に対するガイドラインはどうなっていますか?」
子供の安全を守るための必須質問です。
⑤怪我やトラブル時の対応マニュアル
「練習中に怪我をした場合や、子供同士のトラブルがあった場合、どのような対応フローになっていますか?」
保険の加入状況と合わせて、危機管理体制をチェックします。
子供の意思を尊重するための親子会議
「ガチでやりたい」か「楽しく続けたい」かのすり合わせ
親が「このチームなら安心」と思っても、子供が「雰囲気が合わない」と感じたら続きません。
体験会の後は、必ず子供に感想を聞きましょう。「コーチの教え方は分かりやすかった?」「先輩たちは楽しそうだった?」
そして、子供自身が「もっと上手くなりたい(ガチ)」のか、「友達と楽しく続けたい(エンジョイ)」のか、本音を引き出すことが大切です。
勉強との両立プランを先に提示させる
地域クラブは活動時間が長くなる傾向があります。「野球をやるなら、勉強も疎かにしない」という約束を、入団前に取り付けておきましょう。
「テスト前は練習を休めるチームなのか」「塾との両立は可能なスケジュールか」も、チーム選びの重要なファクターです。
まとめ:地域移行は「親子の選択」が試される時代への入り口
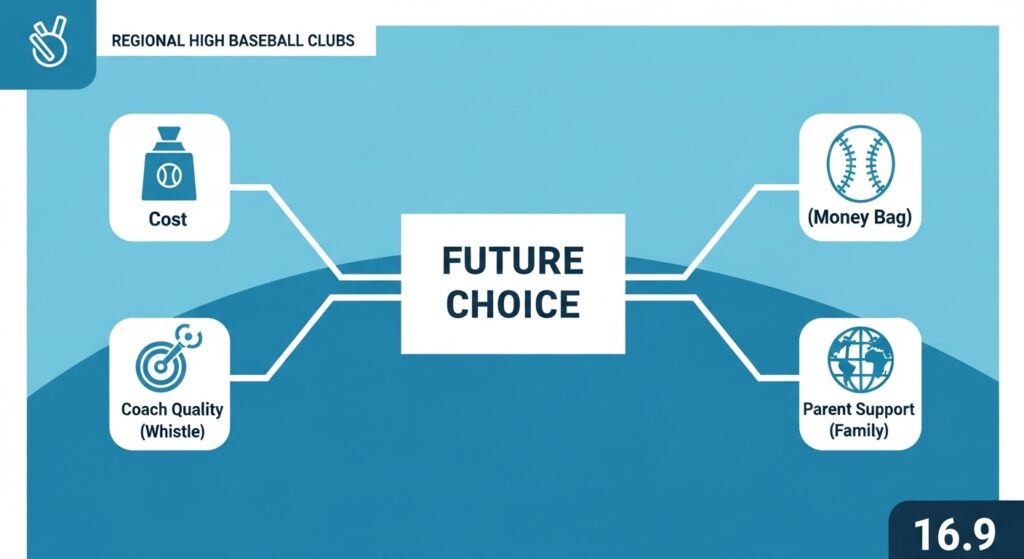
「中学野球の部活地域移行」について、制度の背景から海外事例、そして親ができる対策まで解説してきました。
これまでは、「地元の公立中に入れば、野球部があって、先生が無料で教えてくれる」のが当たり前でした。しかし、そのシステムは限界を迎え、今、新しい形へと生まれ変わろうとしています。
【今回の要点まとめ】
- 2026年度から本格移行: 今は過渡期。自分の地域の進捗を確認しよう。
- 選択肢が増える: 「部活」だけでなく、多様な「地域クラブ」から選べるようになる(硬式・軟式の垣根も低くなる)。
- 負担は増えるが質も上がる: 費用や送迎の負担は増えるが、専門的な指導を受けられるメリットもある。
- NPBも応援している: プロ野球界もこの改革をバックアップし、指導者派遣などを始めている。
- 親の「選ぶ力」が重要: 子供の性格と家庭の事情に合ったチームを、親が見極める必要がある。
正直、変化は怖いです。面倒です。
でも、これを「子供にとって最高の野球環境を、親が一緒に選んであげられるチャンス」と捉えてみてはどうでしょうか。
アメリカのようにシーズン制で他のスポーツを楽しむもよし。ドイツのように地域の人たちと交流しながら楽しむもよし。ドミニカのようにプロを目指してストイックに打ち込むもよし。
日本の野球も、そんな多様性のある未来へ向かっている最中なのかもしれません。
私たち親にできることは、正しい情報を持ち、子供の「野球が好き」という気持ちを一番近くで守ってあげること。
この激変の時代を、親子で会話を重ねながら、二人三脚で乗り越えていきましょう!
さあ、まずは今週末、お子さんと一緒に地域のチームの体験会に行ってみませんか?

