「すごい!」で終わらせない!プロ野球の「ホールド」から学ぶ、少年野球で本当に評価されるべき選手とは?
導入:我が子が試合で活躍できない…その悩み、「ホールド」という視点が解決します
「どうして、うちの子は試合でなかなか活躍できないんだろう…」
週末のグラウンド、我が子の背中を見つめながら、そう胸の内で呟いた経験はありませんか?ヒットを打つわけでもなく、三振を奪うわけでもない。チームメイトの華々しい活躍を横目に、唇を噛み締める我が子と、それを見つめることしかできない自分。
そのもどかしい気持ち、私も痛いほどわかります。
先ほどの音声での野球パパ仲間との会話、いかがでしたか?
ヒットの本数や防御率といった「目に見える数字」だけで子供の価値を判断してしまい、知らず知らずのうちに我が子を追い詰めてしまう…。これは、多くの野球パパが抱える共通の悩みです。
この音声で触れた、プロ野球の「ホールド」という記録。
この記事では、この「ホールド」という考え方をヒントに、スコアブックには決して記録されない我が子の「本当の価値」を見つけ、それを絶大な自信に変えるための具体的な方法を、私の失敗談も交えながら徹底的に解説していきます。
補欠だった息子が、たった一言の「声」でチームを救い、ヒーローになった日。その実体験から見つけ出した「答え」のすべてを、この記事に詰め込みました。
「うちの子、全然目立たない…」多くの野球パパが抱える共通の悩み
少年野球の世界は、時として残酷なほどに結果がすべてに見えてしまいます。
チームのエースで4番。誰もが憧れるヒーローは、いつもグラウンドの真ん中で輝いています。その一方で、声がかかるのは試合終盤のワンポイントや、代走の時だけ。あるいは、最後までベンチを温め続ける子も少なくありません。
親として、我が子が活躍する姿を見たいと願うのは当然のことです。しかし、その願いが強すぎるあまり、私たちはいつの間にか「評価のモノサシ」を一つしか持てなくなってしまいます。
- 「なんであんなボール球を振るんだ!」
- 「もっと自信を持ってプレーしろ!」
- 「〇〇君は、あんなにすごいヒットを打ったのに…」
こんな言葉を、つい口にしてしまったことはないでしょうか。これらはすべて、子供を励ますどころか、その心を深く傷つけ、野球そのものから遠ざけてしまう危険な言葉です。子供自身が、誰よりも悔しい思いをしているにもかかわらず、です。
プロ野球の「ホールド」に隠された、”見えない貢献”を評価するヒント
そんな悩みのループから私を救ってくれたのが、プロ野球の「ホールド」という記録でした。
「ホールド」とは、簡単に言えば、試合の途中で登板する中継ぎ投手の貢献度を評価するための指標です。先発投手のように「勝利」がついたり、抑え投手のように「セーブ」がついたりするわけではありません。しかし、彼らがいなければ、現代野球の勝利は成り立たない。そんな「縁の下の力持ち」に光を当てるための、いわば「見えない貢献」を可視化する記録なのです。
この「ホールド」という考え方を知った時、頭をガツンと殴られたような衝撃を受けました。
「待てよ。少年野球にも、スコアブックには決して記録されないけれど、チームの勝利に欠かせない『隠れた貢献』があるんじゃないか?」
そう気づいた瞬間、目の前の霧が晴れていくような感覚を覚えたのです。
この記事を読めば、数字以外の我が子の「価値」を見つけ、伝える方法がわかります
この記事では、プロ野球の「ホールド」という記録を切り口に、少年野球における「数字以外の価値」の見つけ方、そしてそれを子供の自信に繋げるための具体的な方法を、私の実体験を交えながら徹底的に解説します。
この記事を最後まで読めば、あなたは以下のことを手に入れることができます。
- 野球未経験でもわかる「ホールド」の本当の意味と重要性
- 「打つ・投げる」以外でチームに貢献する5つの具体的な観察ポイント
- 子供の自己肯定感を劇的に高める、魔法の「承認」テクニック
- 他人と比較せず、我が子だけの「価値」を心から応援できるようになる思考法
もう、週末のグラウンドで無力感に苛まれる必要はありません。ヒットを打てなくても、三振を奪えなくても、あなたの息子さんは必ずチームに貢献しています。その「隠れた価値」に光を当てるための、新しい「評価のモノサシ」を、この記事で手に入れてください。
補欠だった息子が「声」でチームを救った、私たちの実体験
偉そうなことを語っていますが、私自身、この「新しいモノサシ」を手に入れるまで、大きな失敗をしました。息子が補欠であることに悩み、彼の努力を正しく評価できず、親子関係がギクシャクしてしまった時期もあります。
しかし、そんな息子が、ある試合でスコアブックには決して残らない「声」という貢献で、負け寸前のチームを救い、ヒーローになった日があります。
その経験が、私に「本当の応援とは何か」を教えてくれました。この記事は、そんな私たちの親子が悩み、失敗し、そして見つけ出した「答え」の集大成です。あなたの親子関係、そして野球との向き合い方を、より豊かで幸せなものにする一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
そもそもプロ野球の「ホールド」って何? 野球未経験パパでも3分でわかる基本のキ

「ホールド、という言葉は聞いたことがあるけど、正直よくわからない…」
野球に詳しくないパパさんなら、そう思うのも当然です。大丈夫です。ここでは、難しいルール解説は一切なし。誰にでもわかるように、「ホールド」のキホンを解説します。
「ホールド」とは? 中継ぎ投手の”試合を保つ”働きを評価する記録
「ホールド(Hold)」とは、その名の通り「保つ」という意味です。何を保つのか? それは、チームのリードです。
プロ野球では、先発投手が一人で9回を投げ切ることは稀で、試合の途中で投手が交代するのが当たり前になっています。この、試合の途中でマウンドに上がる投手を「中継ぎ投手(リリーフ投手)」と呼びます。
ホールドは、この中継ぎ投手が、
- チームがリードしている場面でマウンドに上がり、
- リードを守ったまま、次の投手にマウンドを譲る
という、非常に重要な役割を果たしたときに与えられる「勲章」なのです。派手さはありませんが、試合の勝敗を左右する、まさに「縁の下の力持ち」の働きを評価するための記録と言えるでしょう。
「勝利」や「セーブ」と何が違う? 縁の下の力持ちが脚光を浴びるまで
投手には「ホールド」以外にも、有名な記録が2つあります。
- 勝利:主に先発投手に与えられる、チームが勝った証。
- セーブ:試合の最終回にリードを守り切った抑え投手(クローザー)に与えられる記録。
昔の野球では、この「勝利」と「セーブ」ばかりが注目されていました。しかし、野球の戦術が進化するにつれて、「試合の序盤を作る先発」と「試合の最後を締める抑え」だけでなく、その「間をつなぐ中継ぎ」の重要性が叫ばれるようになりました。
そこで、これまで評価されにくかった中継ぎ投手の貢献に光を当てるため、2005年から日本のプロ野球でも正式に導入されたのが「ホールド」なのです。これにより、これまで目立たなかった選手たちの価値が正しく評価されるようになりました。
なぜ「ホールド」が重要に? 現代野球における「継投」の常識
「一人のエースが最後まで投げ抜く」というのは、もはや過去の野球です。
現代のプロ野球では、各投手の役割を細かく分担し、リレー形式でつないでいく「継投(けいとう)」が勝利のセオリーとなっています。
- 先発投手が試合の土台を作り(5~6回)、
- 中継ぎ投手がリードを守り(7~8回)、
- 抑え投手が試合を締めくくる(9回)。
この流れの中で、一人でも欠けたら勝利は手繰り寄せられません。特に、試合が最も緊迫する終盤、相手チームに流れが傾きかけた苦しい場面でマウンドに上がるのが中継ぎ投手です。彼らが相手の攻撃をピシャリと抑え、リードを「保つ」ことで、初めて最終回の抑え投手へとバトンが渡るのです。
ホールドという記録は、この「勝利の方程式」に欠かせない、極めて重要なピースの価値を示しているのです。
2024年シーズンの記録から見る「最強の中継ぎ投手」の凄み
例えば、2024年のプロ野球セ・リーグを見てみましょう。阪神タイガースの岩崎優投手や読売ジャイアンツの西舘勇陽投手、中日ドラゴンズの松山晋也投手などが、シーズンを通して40個近いホールドを記録し、「最優秀中継ぎ投手」のタイトルを争いました。
40ホールドという数字は、単純計算で「40試合、チームがリードした緊迫した場面でマウンドに上がり、リードを守り切った」という証です。年間143試合しかない中で、これだけの貢献をしている投手がいる。彼らのような「最強の中継ぎ投手」がいなければ、チームの優勝は絶対にありえません。
このように具体的な数字を見ることで、ホールドがいかに価値のある記録か、お分かりいただけるのではないでしょうか。
少年野球はプロ以上に「中継ぎ」が重要である理由
そして、この話は少年野球にこそ、より深く当てはまります。なぜなら、少年野球には「投球数制限」という絶対的なルールがあるからです。
成長期の子供たちの肩や肘を守るため、一人の投手が投げられる球数は厳しく制限されています。つまり、一人のエースが最後まで投げ抜くことは、制度上、不可能なのです。
そうなると、試合に勝つためには、プロ野球以上に複数の投手による「継投」が必須となります。
- 先発したエースが球数制限に達した後、誰がマウンドに上がるのか?
- エラーで流れが悪くなった場面で、雰囲気を変えるために登板するのは誰か?
- リードした最終回、逃げ切るためにマウンドを託されるのは誰か?
試合の途中で登板する投手、つまり「ホールド」的な役割を担う選手の存在が、チームの勝敗を直接的に左右すると言っても過言ではありません。エースでなくとも、試合の重要な局面を任され、チームの勝利に貢献できるチャンスが、少年野球にはたくさん転がっているのです。
【体験談】息子が補欠からチームの「声のホールド王」になった日
ここからは、少し私の個人的な話をさせてください。
この「ホールド」という視点が、いかに私と息子の関係を救ってくれたか。そして、スコアブックに残らない貢献が、いかにチームにとって価値あるものだったか、という実体験です。
「なんで俺だけ試合に出られないんだ…」息子の涙と親として感じた無力感
息子は、小学4年生で野球を始めましたが、決して運動神経が良い方ではありませんでした。周りの子がどんどん上達していく中、息子はいつもみんなの後ろを追いかけているような状態。高学年になっても、その差は埋まるどころか開く一方で、当然のようにレギュラーにはなれず、ベンチを温める日々が続きました。
練習から帰ってきた車の中、黙り込む息子。家についても、部屋に閉じこもってしまう。そしてある夜、布団の中で静かに泣いている息子の背中を見つけてしまったのです。
「なんで…なんで俺だけ試合に出られないんだ…」
絞り出すようなその声を聞いた時、親として何もしてあげられない無力感に、胸が張り裂けそうになりました。練習に付き合うことはできても、彼の代わりに試合に出てあげることはできない。当時の私は、完全に「結果至上主義」のモノサシしか持っておらず、ただ「もっと頑張れ」と無責任に励ますことしかできませんでした。
スコアブックには絶対に残らない貢献のはじまり
そんな苦しい日々が続く中、ある練習試合でのことです。
相変わらずベンチスタートの息子。私は内心、「今日も出番はないだろうな…」と諦めにも似た気持ちでグラウンドを眺めていました。
しかし、その日の息子は、いつもと少しだけ違いました。ベンチの一番前に立ち、誰よりも大きな声を出していたのです。
「ピッチャー、楽に行こうぜ!」
「バッター集中!」「ナイスカット!」
「ランナー、リードいいよ!」
攻撃の時も、守備の時も、彼の声は途切れることがありませんでした。正直、最初は「試合に出られないから、せめて声だけでも出しているのか…」と、少し可哀想にさえ思っていました。その「声」に、特別な価値があるとは、夢にも思っていなかったのです。
「お前の声、ベンチだけじゃなく野手にも届いてるぞ!」監督からの一言
試合は、1点を争う緊迫した展開。エラーをきっかけに、じわじわと相手に流れが傾きかけていました。内野手たちの顔からは笑顔が消え、明らかに浮き足立っています。ベンチの雰囲気も重くなり、誰もが下を向きかけた、その時です。
息子の声が、ひときわ大きくグラウンドに響き渡りました。
「まだ終わってねぇぞ!ここから集中していこう!俺たちが一番強いんだから!」
その瞬間、ハッとしたように内野手たちが顔を上げ、ピッチャーが息子の方を見て、小さく頷いたのが見えました。そして、試合後に監督が息子を呼び止め、肩を叩きながらこう言ったのです。
「今日の試合、お前の声がなかったら、あそこで完全に流れを持っていかれてたぞ。お前の声は、ベンチだけじゃなく、ちゃんと野手にも届いてる。ありがとうな」
劣勢ムードを変えた絶叫-その日、息子は紛れもなくチームのヒーローだった
監督からの言葉は、魔法のようでした。
次の試合でも、息子はベンチから声を出し続けました。そして、運命の試合が訪れます。
地区大会の決勝戦。最終回、1点リードで迎えた最後の守り。しかし、先頭打者にヒットを許し、エラーも絡んでノーアウト2,3塁という絶体絶命のピンチを招きます。球場の誰もが「サヨナラ負けか…」と諦めかけた、その時でした。
タイムがかかり、マウンドに集まる内野手たち。その輪に向かって、息子がベンチから叫びました。
「みんな、俺の声を聞けーっ!練習でやってきたことだけやれば絶対抑えられる!自信持っていこうぜぇぇぇ!」
それは、もはや声援ではなく、魂の絶叫でした。その声に呼応するように、マウンド上の選手たちが「おう!」と力強く応え、顔つきが変わったのが分かりました。結果、後続を内野ゴロ、三振、ピッチャーフライに打ち取り、奇跡的な勝利を掴んだのです。
スコアブックに残ったのは、最後に投げたピッチャーの「セーブ」記録だけ。でも、あの日、あの場所で試合を見ていた誰もが分かっていました。あの重苦しい雰囲気を断ち切り、チームに勇気を与え、勝利の流れを「保った」のは、間違いなくベンチにいた息子の「声」だった、と。
「あいつの声があったから打てた」チームメイトからの感謝が自信に変わった瞬間
試合後、息子はチームメイトたちに囲まれていました。
「お前の声、マジで助かったわ。ありがとう!」
「あいつの声があったから、落ち着いて守れたよ」
「次の打席、俺にも声援頼むな!」
ヒーローインタビューを受けるかのように、仲間たちから次々と感謝の言葉をかけられる息子。その顔は、今まで見たことがないほど誇りと自信に満ち溢れていました。ヒットを打ったわけでも、ファインプレーをしたわけでもない。それでも彼は、紛れもなくチームの中心にいたのです。
親として気づいた痛恨のミス-評価のモノサシは一つではなかった
その光景を見て、私は自分の愚かさに気づき、涙が止まりませんでした。
私はずっと、息子に「試合に出て活躍すること」だけを求めていました。ヒットや得点という、目に見える結果ばかりを追い求めていた。しかし、息子はとっくに自分だけの「価値」を見つけ、チームに貢献していたのです。
スコアブックには残らない。誰の記憶にも残らないかもしれない。でも、チームの勝利に欠かせない、声の「ホールド」。それは、どんなスーパープレーにも劣らない、尊い貢献でした。
評価のモノサシは、決して一つではなかった。それに気づけず、息子を苦しめていたのは、他の誰でもない、父親である私自身だったのです。
我が子だけの「隠れホールド」を発見!今日から使える5つの観察チェックリスト

息子の体験は、特別なことではありません。あなたのお子さんも、必ず何らかの形でチームに貢献しています。それに気づけるかどうかは、親である私たちが「評価のモノサシ」をいくつ持てるかにかかっています。
ここでは、野球未経験のパパでも今日から実践できる、我が子だけの「隠れホールド」を発見するための具体的な観察チェックリストを5つのシーンに分けてご紹介します。
評価軸をずらしてみよう-「打つ・投げる」以外の価値を見つける準備
まず大切なのは、意識の変革です。
グラウンドを見つめる時、ボールの行方だけを追うのをやめてみましょう。打球が飛んでいない時、自分の子供が打席に立っていない時こそ、絶好の観察チャンスです。
「息子は今、何をしているだろう?」
「どんな表情で、誰と話しているだろう?」
「チームのために、何か行動していることはないだろうか?」
この視点を持つだけで、今まで見えていなかった我が子の姿が、次々と目に飛び込んでくるはずです。
【ベンチ編】声出しだけじゃない!仲間への気配り、準備・片付けの率先
ベンチは、「隠れホールド」の宝庫です。試合に出ていなくても、貢献できることは無限にあります。
- ✅ 誰よりも大きな声で、仲間を励まし続けているか?
- ✅ ピッチャーがマウンドに行く時、「頑張れよ!」と背中を叩いているか?
- ✅ タイムの時、真っ先に伝令に走ろうとしているか?
- ✅ 仲間の水筒を集めたり、道具を整理したりしているか?
- ✅ 試合の準備や後片付けを、誰に言われるでもなく率先してやっているか?
- ✅ ファールボールを全力で追いかけているか?
これらはすべて、チームの士気を高め、円滑な運営を支える立派な「ホールド」です。
【守備編】打球が飛んでこなくてもできる貢献-的確なカバーリングと声かけ
守備の貢献は、ファインプレーだけではありません。打球が自分に飛んでこない「9割の時間」にこそ、選手の価値は表れます。
- ✅ ピッチャーが投げるたびに「さあ来い!」と声を出して盛り上げているか?
- ✅ 自分のポジションに関係ない打球でも、カバーリングのために走っているか?
- ✅ エラーした仲間に対して「ドンマイ!」とすぐに声をかけているか?
- ✅ アウトカウントやランナーの状況を、周りの選手に伝えているか?
- ✅ 常にプレーの次の展開を予測し、準備を怠らない姿勢があるか?
特にカバーリングは重要です。万が一のエラーに備えて全力で走る姿は、チームに安心感と連帯感をもたらす、最高の「ホールド」と言えるでしょう。
【走塁編】ヒットを打てなくてもチームに勢いを-全力疾走と次の塁を狙う姿勢
たとえ平凡な内野ゴロでも、アウトになることが分かっていても、一塁まで全力で走り抜ける。この姿勢は、相手野手にプレッシャーを与え、エラーを誘発する可能性があります。
- ✅ どんな打球でも、一塁まで全力で走り抜けているか?
- ✅ 相手の隙を見て、常に次の塁を狙う意識が見えるか?
- ✅ ランナーコーチとして、的確な指示と大きな声を出しているか?
- ✅ 自分がアウトになった後、悔しがるだけでなく、すぐにベンチに戻り応援に切り替えているか?
全力疾走は、見ている仲間の心を打ち、チーム全体の士気を高めます。「あいつが頑張っているんだから、俺も頑張ろう」と思わせる、伝染する「ホールド」なのです。
【練習編】一番の成長機会-苦手な練習への取り組み、仲間へのアドバイス
試合だけでなく、日々の練習にも「隠れホールド」は隠されています。むしろ、子供の本当の姿は練習態度にこそ表れるものです。
- ✅ 自分が苦手な練習から逃げずに、黙々と取り組んでいるか?
- ✅ 仲間がうまくできない時、馬鹿にせず、アドバイスを送っているか?
- ✅ 指導者の話を、真剣な眼差しで聞いているか?
- ✅ 練習のための準備(グラウンド整備や道具出し)を率先して行っているか?
- ✅ 誰よりも早くグラウンドに来て、自主練習をしているか?
これらの地道な努力は、すぐには結果に結びつかないかもしれません。しかし、チームメイトや指導者は、必ずその姿を見ています。その真摯な姿勢が、チーム全体の練習の質を高める、かけがえのない「ホールド」なのです。
見つけた価値を自信に変える!野球パパが実践すべき「承認」の技術
チェックリストを使って我が子の「隠れホールド」を見つけたら、次が最も重要なステップです。それは、見つけた価値を子供に「伝え」、自信に変えてあげることです。
この「伝え方」を間違えると、せっかくの発見も台無しになってしまいます。ここでは、子供の自己肯定感を育むための「承認」の技術をお伝えします。
絶対NG!他人との比較や結果だけを求める言葉が子どもの心を壊す
まず、絶対にやってはいけないことから確認しましょう。それは「他人との比較」です。
「〇〇君はホームランを打ったのに、なんでお前は打てないんだ」
「レギュラーの〇〇君を見習え」
これらの言葉は、百害あって一利なしです。子供は「自分は〇〇君より劣っているんだ」「今の自分はダメなんだ」と感じ、自信を完全に失ってしまいます。
また、「結果だけ」を求める言葉も危険です。「ヒットを打てて良かったな」「エラーするなよ」といった声かけは、子供に「結果を出さなければ認められない」というプレッシャーを与え、プレーを萎縮させてしまいます。
最高の褒め言葉は「見てるよ」-プロセスを具体的に伝えるフィードバック術
では、どう伝えれば良いのでしょうか。ポイントは、「結果」ではなく「プロセス」を、具体的に褒めることです。
「ナイスバッティング!」という漠然とした褒め言葉よりも、
「あの難しいボールに食らいついて、ファールで粘ったのが凄かったね!次のヒットに繋がるよ」
「よく守ったな!」よりも、
「打球は飛んでこなかったけど、毎回ピッチャーが投げるたびにしっかり準備して、カバーにも走ってたね。パパは、ちゃんと見てたよ」
このように、親が自分のどんな行動を「見ていてくれた」のかを具体的に伝えることで、子供は「自分の頑張りは認められているんだ」と実感し、強い自己肯定感を育むことができます。
最高の褒め言葉は「すごいね」ではありません。「パパは、ちゃんと見てるよ」というメッセージなのです。
親子で「今日のファインプレー」を振り返る野球ノートのススメ
具体的なフィードバックを習慣化するために、「野球ノート」の活用を強くお勧めします。
練習や試合から帰ってきた後、親子でノートを広げ、「今日のファインプレー」について話し合うのです。ここでの「ファインプレー」は、ヒットや好守備に限りません。
「今日、ベンチから一番声が出てたのは間違いなくお前だったな!」
「エラーした〇〇君に、一番最初に『ドンマイ』って声をかけたお前の姿、かっこよかったぞ」
このように、親が見つけた「隠れホールド」を記録していくのです。もちろん、子供自身にも自分の良かったプレーを書かせましょう。これを続けることで、子供は自然と「数字以外の価値」に目を向けるようになり、主体的に自分の役割を探すようになります。
「あの子の〇〇がチームを助けています」指導者とのポジティブな情報共有術
もう一つ、非常に効果的なのが、指導者との情報共有です。
練習の送り迎えの際などに、「監督、いつもありがとうございます。うちの子、家では『〇〇君のカバーリングがすごい』ってよく話してるんですよ」というように、ポジティブな情報を伝えてみましょう。
また、勇気を出して「うちの子、なかなか試合では結果が出ないですけど、家では素振りも頑張っていますし、チームのために声を出すことを自分の役割だと思っているようです」と伝えてみるのも良いでしょう。
指導者は、多くの選手を見ているため、一人ひとりの細かい変化や努力を見逃していることもあります。親からの情報提供は、指導者がその子の新しい側面を知る良いきっかけになります。指導者から「お前の頑張り、お父さんから聞いたぞ。ちゃんと見てるからな」と声をかけられたら、子供のモチベーションが爆発的に上がることは間違いありません。
「ホールド」的視点がもたらす、チームと子どもの未来への3つの好影響
これまでお伝えしてきた「ホールド」的な視点、つまり「見えない貢献」に光を当てるという考え方は、単に子供のやる気を引き出すだけでなく、チーム全体、そして子供の未来にも素晴らしい影響を与えます。
勝利至上主義からの脱却と「全員野球」の本当の意味
「全員野球」という言葉は、よく使われます。しかし、その本当の意味を理解しているチームは意外と少ないのではないでしょうか。
「ホールド」的視点がチームに浸透すれば、選手たちは自然と、自分以外の選手の貢献にも目を向けるようになります。
「あいつの声があったから、ピンチを乗り越えられた」
「あいつが全力疾走したから、相手のエラーを誘えた」
このように、互いの「隠れホールド」を認め合い、感謝し合う文化が生まれれば、チームは本当の意味での「全員野球」を実践できる、強い組織へと成長していくでしょう。勝利やレギュラー争いだけが全てではない、という価値観がチーム全体を優しく包み込みます。
自己肯定感の向上-野球人生の財産になる「自分の役割を見つける力」
少年野球は、子供の人生のほんの通過点に過ぎません。中学、高校と野球を続ける子もいれば、別の道に進む子もいます。
どちらの道に進むにせよ、少年野球時代に「自分なりの役割を見つけ、チームに貢献した」という成功体験は、その子の人生にとって、かけがえのない財産になります。
勉強、部活、そして将来の仕事。どんなコミュニティにおいても、必ずしも全員が主役になれるわけではありません。しかし、「自分には自分の価値がある」「自分はこの組織にこう貢献できる」と信じられる力、すなわち高い自己肯定感さえあれば、どんな環境でも自分の居場所を見つけ、輝くことができるはずです。
親子の絆が深まる-同じ視点で応援できる喜び
そして何より、「ホールド」的視点は、私たち親子の関係をより深いものにしてくれます。
結果に一喜一憂し、子供にプレッシャーをかけてしまう関係から、子供の小さな努力や成長を見つけ、それを承認し、共に喜ぶ関係へ。
「今日のあの声かけ、最高だったな!」
「あのカバーリング、見てたぞ!」
試合後、そんな会話をしながら帰る車内は、きっと温かい空気に満ちているはずです。同じ方向を向き、同じ価値観で我が子を応援できる喜び。それは、野球が私たち親子に与えてくれる、最高のプレゼントなのかもしれません。
まとめ
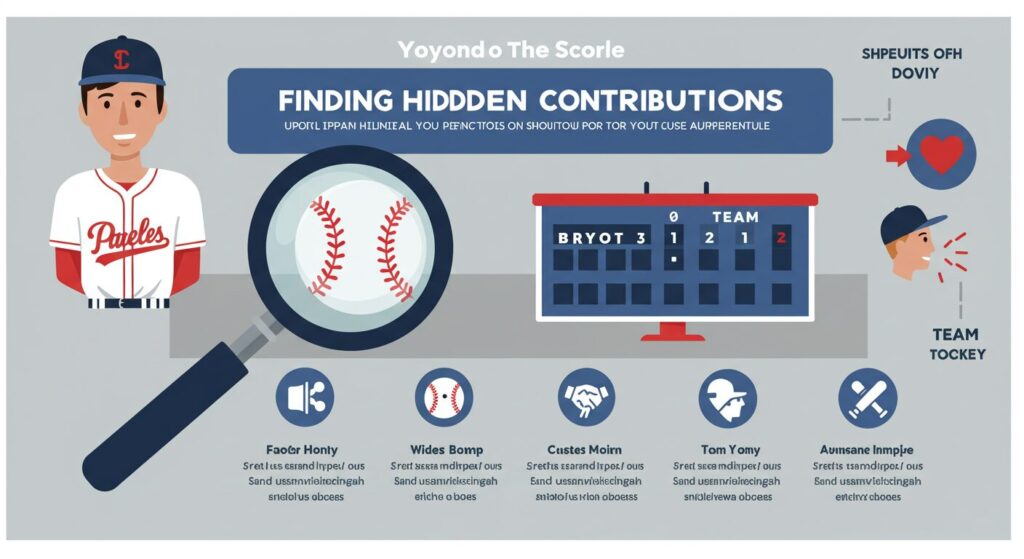
最後に、この記事の要点をもう一度振り返ります。
プロ野球の「ホールド」は、”見えない頑張り”に光を当てるための指標
プロ野球の「ホールド」は、これまで評価されにくかった中継ぎ投手の「縁の下の力持ち」的な貢献を可視化するために生まれました。この考え方は、少年野球においても、スコアブックに残らない子供たちの価値を見つけるための大きなヒントとなります。
スコアブックに残らなくても、あなたの子供は必ずチームに貢献している
ヒットを打てなくても、三振を奪えなくても、心配する必要はありません。あなたのお子さんは、声出し、カバーリング、全力疾走、練習態度など、様々な形で必ずチームに貢献しています。大切なのは、親である私たちが、その「隠れた価値」に気づいてあげることです。
評価のモノサシを増やし、我が子だけの「価値」を見つけ、伝えよう
「打つ・投げる」という一つのモノサシだけで子供を評価するのは、今日で終わりにしましょう。この記事で紹介した5つの観察チェックリストを参考に、あなただけの「評価のモノサシ」を増やしてください。そして、見つけた価値を「ちゃんと見てるよ」という具体的な言葉で伝え、子供の自信を育んであげましょう。
あなたからの「承認」こそが、子どもの野球人生における最高の”ホールド”になる
子供にとって、一番の応援団は、他の誰でもない、親であるあなたです。
他人と比較することなく、我が子だけの「価値」を信じ、承認し続けること。それこそが、子供の揺れる心を守り、未来へとつなぐ、最高の「ホールド」になるはずです。
週末のグラウンドが、あなたと息子さんにとって、苦しい場所ではなく、成長と喜びに満ちた最高の舞台になることを、心から願っています。

