山本由伸はなぜ完投できる?少年野球の常識を覆す「投げない」勇気と驚異のスタミナの秘密
導入:現代野球の常識を覆した、歴史的な「完投劇」
2025年10月、野球界の常識が覆る歴史的な一投が投じられました。ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が、ポストシーズンという最高の舞台で圧巻のメジャー初完投勝利。
なぜ分業制が主流の現代MLBで、彼は1人で投げ抜くことができたのか?
本文に入る前に、まずは野球パパ仲間との「立ち話」から。この記事の核心に触れる、ポッドキャスト風の音声解説をお聞きください。
音声でお話した通り、彼の強さの秘密は、日本の少年野球界に根強く残る「投げ込み至上主義」へのアンチテーゼにありました。
ここからは、山本投手の少年時代から現在に至るまでの哲学、トレーニング、メンタル術を徹底的に解剖し、少年野球の選手と、その成長を願うパパたちへの具体的なヒントを提示していきます。
「力まない」投球哲学が生んだ圧倒的な効率性
山本投手の「完投能力」を解き明かす上で、最初のキーワードは「力まない」ことです。意外に思われるかもしれませんが、彼の驚異的なスタミナは、全力で腕を振ることではなく、いかに無駄な力を使わないか、という哲学から生まれています。
プロ入り当初の苦悩:「5回で体がパンパンになった」過去
今でこそ球界を代表する投手となった山本投手ですが、プロ入り当初はスタミナ不足に苦しんでいました。一軍初登板を果たしたルーキー時代、彼は自らの体について「5回を投げただけで体がパンパンになってしまった」「スタミナがない」と感じていたと、過去のインタビューで明かしています。
当時の彼は、持てる力のすべてをボールに伝えようと、全力で腕を振り、体を酷使していました。しかし、その結果待っていたのは、早期のガス欠と、プロの世界で戦い抜くことへの大きな壁だったのです。この経験が、彼の投手人生における最初の、そして最も重要なターニングポイントとなりました。
「力まずに質の高い球を」への思考転換
大きな壁にぶつかった山本投手は、あるシンプルな結論にたどり着きます。
「力まなければいい。力まずに質の高い球が投げられればいい」
これは、単なる発想の転換ではありません。自身のピッチングをゼロから見つめ直し、力の使い方を根本的に再設計するという、大きな挑戦の始まりでした。彼は、肩や肘といった特定の部位に負荷を集中させるのではなく、体幹や下半身からのエネルギーを、波が伝わるようにスムーズにボールへと集約させることを目指したのです。
無駄な力みをなくし、体の機能を最大限に活かす。この効率性を追求したアプローチこそが、9回を投げ抜いても球威が衰えない、驚異的なスタミナの土台を築き上げました。
少年野球に置き換える「量より質」:球数ではなく”再現性”を求める意味
この山本投手の哲学は、少年野球にこそ大きな示唆を与えてくれます。
多くのチームでは、今も「スタミナをつけるため」「根性を鍛えるため」といった理由で、多くの球数を投げ込ませる練習が行われています。しかし、山本投手の例は、「スタミナ=投げ込みの量」ではないという事実を明確に示しています。
本当に大切なのは、何球投げたかではありません。たった1球でも、自分の理想とするフォームで、狙った場所に投げられるかという「再現性」です。
疲労困憊の状態で投げ続けても、フォームは崩れ、コントロールは定まらず、最悪の場合、怪我につながるだけです。それよりも、集中力が続く範囲で、一球一球、体の使い方を確認しながら投げる方が、よほど効率的で、将来につながる本当のスタミナを育むことができるのです。
全身を連動させる「しなやかな」投球メカニクス

山本投手の「力まない」哲学を、技術的に支えているのが、全身を巧みに連動させる、しなやかな投球メカニクスです。彼は、腕や肘を単なる「ボールを投げるための道具」ではなく、体が生み出したエネルギーの最終的な出口として捉えています。
肘への負担を減らす「やり投げ」トレーニングの秘密
山本投手が実践しているユニークなトレーニングの一つに「やり投げ(ジャベリックスロー)」があります。野球選手がなぜやり投げを?と疑問に思うかもしれません。しかし、これこそが彼のフォームの核心に迫る重要な練習なのです。
やり投げは、腕の力だけで遠くに投げることはできません。助走の勢いを止めずに、体幹をバネのように使い、下半身から上半身、そして腕へとスムーズに力を伝達させる「全身の連動」が不可欠です。
山本投手はこのトレーニングを通して、「肘を主体として使わない」感覚を養っています。ボールを投げるとき、多くの選手は無意識に肘を支点にして腕を振ろうとしますが、これは肘に多大な負担をかけ、怪我のリスクを高めるだけでなく、エネルギーのロスにもつながります。やり投げの動きは、この「肘への依存」から脱却し、体全体を一つの大きな弓のように使ってボールを射出する感覚を体に覚え込ませるのです。
体幹と重心を操る「BCエクササイズ」とは?
彼の身体の使い方を支えるもう一つの柱が「BCエクササイズ」です。これは、体の中心(体幹)を意識し、重心を巧みにコントロールしながら動作を行うトレーニングです。
例えば、不安定な足場でバランスを取りながら、ゆっくりと投球動作に近い動きを繰り返す。地味に見えるこの練習が、マウンドという常に変化する状況下で、常に安定したフォームを維持するための土台となります。
ピッチングは、片足で立った状態から爆発的な力を生み出す、非常に高度なバランス能力が求められる動作です。体幹が弱く、重心がブレていては、せっかく生み出した力も地面に逃げてしまい、ボールに効率よく伝わりません。BCエクササイズは、この力の伝達効率を最大化し、「力まない」状態でも質の高いボールを投げることを可能にするのです。
なぜ彼は過度なウエイトトレーニングをしないのか
山本投手は、一般的なプロ野球選手が取り組むような、高重量のウエイトトレーニングを極端には重視しないことでも知られています。これも彼の哲学の表れです。
彼が目指すのは、筋肉を大きくしてパワーで圧倒すること(筋肥大)ではありません。あくまでも、自分の体を思い通りに、そして効率的に動かすための「機能的な筋肉」を鍛えることです。
重いバーベルを持ち上げる力よりも、投球動作の中で必要な関節の可動域を確保し、その範囲内で安定して力を発揮できること。筋肉の鎧で体を固めるのではなく、しなやかなバネのような体を作り上げる。この考え方が、彼の怪我の少なさと、シーズンを通して安定したパフォーマンスを維持できる秘訣の一つと言えるでしょう。
“投げる”以外の時間を支配する、独自のトレーニングと調整法
完投能力は、マウンドの上だけで作られるものではありません。むしろ、投げていない時間をいかに過ごすか、その「調整法」こそが、試合終盤でのパフォーマンスを大きく左右します。山本投手は、独自の調整法で自らの体を完璧にマネジメントしています。
専属トレーナーと取り組む「奇妙な」アイソメトリック
山本投手は、専属の矢田修トレーナーと共に、非常にユニークなトレーニングに取り組んでいます。ドジャースの同僚投手が「クレイジーで奇妙だ」と表現したそのトレーニングの一つが「アイソメトリック」です。
これは、筋肉の長さを変えずに力を入れ続けるトレーニング法で、例えば、壁を押したり、動かないものを引っ張ったりする動きがこれにあたります。山本投手は、あえて不安定で力の入りにくい体勢を作り、その状態で一定時間耐え続ける、といった高度なアイソメトリックを実践しています。
このトレーニングの目的は、単なる筋力強化ではありません。肉体的に苦しい状況でも、精神を集中させ、体をリラックスさせる能力を鍛えることにあります。試合終盤、疲労がピークに達した場面でも、冷静に自分の体をコントロールできる精神的な強さは、こうした地道なトレーニングによって育まれているのです。
可動域と安定性の両立:ブリッジがもたらす光と影
山本投手の代名詞とも言えるトレーニングが「ブリッジ」です。彼は、驚異的な柔軟性で美しいアーチを描きます。このブリッジは、肩甲骨周りや股関節の柔軟性を高め、投球に必要な「しなり」を生み出す上で非常に有効です。
しかし、専門家の中には、このブリッジの「やりすぎ」に警鐘を鳴らす声もあります。可動域を広げすぎると、逆に関節が不安定になったり、体幹の力が抜けやすくなったりするリスクがあるためです。
山本投手自身もその点は深く理解しており、単に体を柔らかくするだけでなく、広げた可動域の中で体を安定させるためのトレーニングを並行して行っています。柔軟性と安定性、この二つを高いレベルで両立させていることこそが、彼のパフォーマンスの真髄なのです。
試合中のベンチでも行う重心コントロールの重要性
彼の調整は、試合中にも及びます。イニングの合間にベンチに戻った山本投手を注意深く見ていると、彼はただ座って休んでいるわけではありません。
立った状態で、ゆっくりと体の重心を確かめるような動きをしたり、軽いストレッチを行ったりしています。これは、数多くの投球で僅かに生じた体の歪みや、重心のズレを即座に修正するための行動です。
自分の体の状態を常に客観的に把握し、最高の状態を維持するために、投げていない時間も思考を止めない。この徹底したプロ意識と自己管理能力が、彼を「完投できる投手」たらしめているのです。
少年時代の「やりすぎない練習」が最強の土台を築いた

山本由伸という投手の原型は、プロ入り後ではなく、そのはるか前、少年時代にすでに形作られていました。彼の強さの本当の秘密は、この時期の「やりすぎない」練習環境と、野球を心から楽しむ心にありました。
中学時代はエースではなかった?「普通の野球少年」の過ごし方
驚くべきことに、山本投手は中学時代、チームの絶対的エースではありませんでした。「どこにでもいる普通の野球少年」、それが当時の彼を知る指導者たちの共通した証言です。彼は、ずば抜けた体格や球速を持っていたわけではなく、むしろコントロールを武器にする繊細なタイプの投手でした。
重要なのは、この時期に周囲の指導者が、彼の将来を見据えて「無理をさせなかった」ことです。体がまだ成長段階にある少年期に、目先の勝利のために過度な投げ込みを強いることは、才能の芽を摘むことになりかねません。山本投手は、指導者の賢明な判断の下、じっくりと、しかし着実に成長するための土台を築く時間を与えられたのです。
山本由伸が没頭した「壁当て」が育む真のコントロール
では、彼は少年時代、どのような練習に打ち込んでいたのでしょうか。彼自身が「やっていて良かった」と振り返るのが、「壁当て」です。
一見、地味で単調なこの練習にこそ、彼のピッチングの原点が詰まっています。壁当ては、相手も、球数も気にする必要がありません。ただひたすらに、自分がイメージした通りのフォームで、壁に描いた的を目がけてボールを投じる。この静かな反復作業が、彼の代名詞である「針の穴を通す」とまで言われる精密なコントロールを育んだのです。
これは、前述した「量より質」「再現性」の追求そのものです。たくさんのボールを投げることよりも、たった一球の質にこだわる。この習慣が、少年時代の山本由伸の体に深く刻み込まれました。
「楽しむ心」が最大のエネルギー源:やらされる練習からの脱却
山本投手は、野球上達の秘訣を聞かれ、「楽しさを忘れないこと」の重要性を繰り返し語っています。
彼にとって練習は、誰かに「やらされる」苦行ではありませんでした。壁当てにしても、ドッジボールにしても、どうすればもっと上手くなるか、どうすればもっと楽しくなるかを常に考え、自ら工夫を重ねる「遊び」の延長線上にあったのです。
この内側から湧き出る「楽しい」という感情こそが、継続的な努力を支える最も強力なエネルギー源となります。厳しい練習を課すだけでは、子供の心はいつか燃え尽きてしまいます。指導者や親が本当にすべきことは、子供自身が野球の楽しさを見出し、自ら「上手くなりたい」と思える環境を整えてあげることなのかもしれません。
痛みがあればすぐ申告:怪我をしない・させない勇気と環境
山本投手の少年時代のエピソードで、もう一つ特筆すべきは、彼が「痛みを感じたら無理せず、すぐに自己申告していた」という点です。
「監督やコーチに言いづらい」「レギュラーから外されたくない」といった理由で、痛みを隠してプレーを続ける選手は少なくありません。しかし、それは将来の選手生命を危険に晒す、非常にリスクの高い行為です。
山本投手には、勇気を持って「痛い」と言える素直さがありました。そして、それを受け入れ、「分かった、休め」と即座に判断できる指導者が周りにいました。この選手と指導者の信頼関係こそが、彼を大きな怪我から守り、今日の活躍へと繋がる道筋を作ったのです。
圧巻のスタミナを支える強靭なメンタルとゲーム術
9回を1人で投げ抜くためには、肉体的なスタミナと同じくらい、いや、それ以上に精神的なスタミナが求められます。山本投手は、マウンド上で常に冷静沈着。その強靭なメンタルの裏側には、緻密な計算と技術が隠されています。
失点しても崩れない「切り替えの技術」
歴史的な完投勝利を収めたあの日、山本投手は初回に先頭打者ホームランを浴びています。並の投手であれば、この一発で動揺し、リズムを崩してしまうところです。しかし、彼は全く動じませんでした。
試合後のインタビューで、彼は「すぐに切り替えて投げられた」と淡々と語っています。これは、彼が常に持ち続けている「切り替えの技術」の賜物です。
彼にとって、過去の結果は変えられないもの。重要なのは、打たれてしまった事実を引きずることなく、次の打者、次の一球に100%集中することです。この思考の切り替えの速さが、大量失点を防ぎ、試合を立て直すことを可能にしています。これは、日々の練習から「一球一球の目的」を明確に意識することでしか養われない、高度なメンタルスキルです。
打者との駆け引きで体力を温存する「省エネ投球」という考え方
山本投手のピッチングを見ていると、常に全力で投げているわけではないことに気づきます。彼は、試合全体の流れを読み、打者の反応を見ながら、巧みに力の入れ具合をコントロールしています。これが「省エネ投球」です。
例えば、下位打線や、追い込んで有利なカウントになった場面では、全力のストレートではなく、少し力を抜いた変化球で打ち取る。一方で、ピンチの場面や、ここ一番の勝負どころでは、ギアを上げて相手を圧倒する。
この巧みなペース配分が、試合終盤まで球威を維持することを可能にしています。完投とは、9回を通して全力で投げ続けることではありません。いかに力を抜くべきところを見極め、勝負どころで最大出力を発揮するかという、クレバーなゲームマネジメント能力の結晶なのです。
厳しい判定にも動じないポーカーフェイスの作り方
メジャーリーグのストライクゾーンは、日本のそれとは異なり、日によって、審判によっても微妙に変化します。多くの日本人投手がこの「動くゾーン」への対応に苦しむ中、山本投手は際立った適応力を見せています。
際どいコースをボールと判定されても、彼は決して表情を崩しません。審判への不満を露わにすることなく、すぐに次の投球に集中します。このポーカーフェイスは、彼のメンタルコントロール能力の高さを示すと同時に、審判や相手チームに余計なプレッシャーを与えないという戦略的な意味も持っています。
コントロールできないもの(審判の判定)に心を乱されるのではなく、自分自身がコントロールできるもの(次の一球)に全ての意識を注ぐ。このシンプルな哲学を徹底できることが、彼の強さの根幹を成しているのです。
家庭で実践!明日から使える「山本由伸流」育成メソッド
山本由伸投手の哲学やトレーニングは、プロの世界だからできる特別なものではありません。その多くは、少年野球の選手と、それを支える保護者が家庭で実践できる、シンプルで本質的なヒントに満ちています。
【練習編】壁当てとドッジボールで野球脳と身体連動を鍛える
・壁当て: 今すぐ、家の壁や公園の壁に、ガムテープなどでストライクゾーンを作ってみましょう。大切なのは球数ではありません。「今日はアウトコース低めに10球、完璧なボールを投げる」といったように、明確な目標を持って取り組むことが重要です。親子でどちらが正確に投げられるか、ゲーム感覚で競争するのも良いでしょう。
・ドッジボール: 週末は、友達や家族とドッジボールを楽しみましょう。ボールから逃げ、体を捻って投げるといった多様な動きは、野球だけでは養われない身体の連動性を高めてくれます。何より、「楽しい」と感じながら体を動かすことが、子供の運動能力を飛躍的に向上させます。
【身体ケア編】投げ込みよりも大切な食事・睡眠・ストレッチ
完投できる体は、練習グラウンドの外で作られます。
・食事: 練習後30分以内は「ゴールデンタイム」です。おにぎりやバナナ、牛乳などで、消費したエネルギー(炭水化物)と傷ついた筋肉を修復する材料(タンパク質)を素早く補給させてあげましょう。
・睡眠: 子供の成長にとって、睡眠は何よりも重要です。体を回復させ、成長ホルモンを分泌させるために、十分な睡眠時間を確保することを徹底してください。
・ストレッチ: お風呂上がりの体が温まった状態で、親子一緒にストレッチをする習慣をつけましょう。特に、股関節や肩甲骨周りの柔軟性を高めることは、怪我の予防とパフォーマンス向上に直結します。
【親の役割編】球数ではなく”表情”を見る:子供の「やりすぎサイン」の見抜き方
親として最も重要な役割は、子供の「やりすぎサイン」にいち早く気づき、ブレーキをかけてあげることです。
練習から帰ってきた子供の表情を見てください。「今日も楽しかった!」と生き生きしていますか?それとも、どこか疲れて、辛そうな顔をしていませんか?
「今日は何球投げたの?」と球数を聞くのではなく、「今日の練習で、一番楽しかったことは何?」と問いかけてみてください。子供が野球に対して前向きな気持ちを失っていると感じたら、それは心と体が悲鳴を上げているサインかもしれません。時には、思い切って「休む」という選択肢を与えることも、親の重要な役割です。
【注意点】山本由伸の全てを真似るべきではない理由
山本投手の取り組みは多くのヒントを与えてくれますが、その全てを鵜呑みにして、そのまま少年野球の子供に当てはめるのは危険です。彼の成功には、彼だからこそ成立した、いくつかの特別な前提条件があることを理解しておく必要があります。
彼だけの特別な身体的特性
まず、山本投手は、プロのアスリートの中でも特に優れた身体的特性を持っています。特に、彼の投球フォームの土台となっている肩甲骨周りや股関節の柔軟性は、誰もが簡単に模倣できるものではありません。無理に同じ動きをしようとすれば、かえって体を痛めてしまう可能性があります。
プロのトレーナーによる万全のサポート体制という前提
彼のユニークなトレーニングは、矢田修トレーナーをはじめとする、体の専門家の知見に基づき、彼の体の状態を精密に分析した上で組み立てられています。専門知識のない指導者や親が、見様見真- なれで同じトレーニングを課すことは、意図しない負荷をかけ、怪我を誘発するリスクを伴います。
成長期の子供への過度なトレーニングがもたらすリスク
大人のトップアスリートと、骨や筋肉がまだ発達段階にある成長期の子供とでは、体のつくりが全く異なります。例えば、過度な可動域の追求は、成長期の子供にとっては関節の不安定性を招くことにもなりかねません。子供の成長段階を無視したトレーニングは、百害あって一利なしです。
フォームに関する一部の批判的視点(アーム投げの指摘)も理解する
華々しい実績の裏で、一部の専門家からは、山本投手のフォームを「アーム投げ(腕の力に頼った投げ方)に近い」と分析し、肩への負担を懸念する声も上がっています。もちろん、これはあくまで一つの見方であり、彼のパフォーマンスがその懸念を払拭しているとも言えます。しかし、絶対的に正しいフォームというものは存在せず、様々な視点があることを理解し、一つの方法論を盲信しないことが重要です。
まとめ
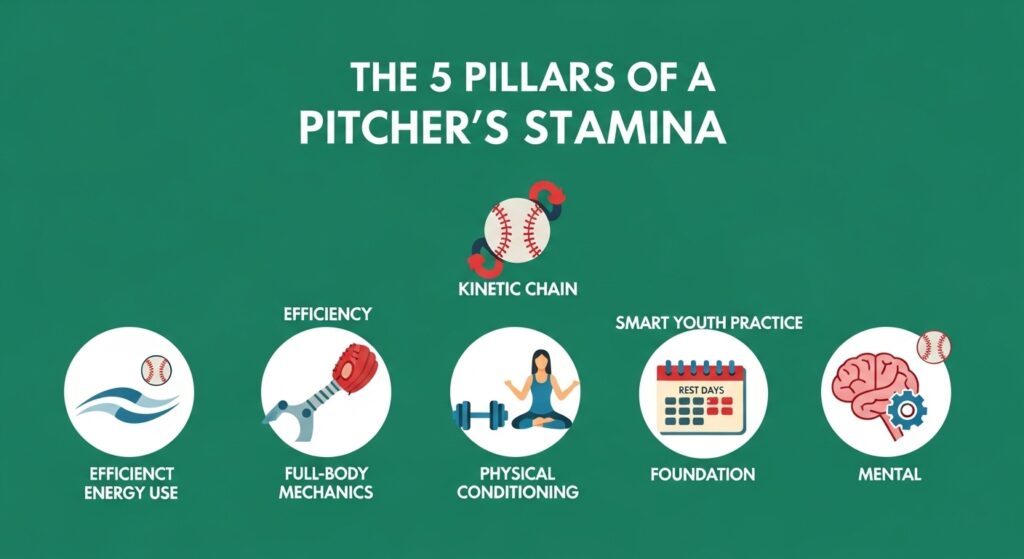
山本由伸投手の歴史的な完投勝利。その力の源泉をたどる旅は、私たちに一つの明確な答えを示してくれました。
彼の驚異的なスタミナは、歯を食いしばって投げ込んだ球数の多さによって得られたものではありません。それは、「量より質」を徹底的に追求した効率的な練習と、それを支える周到なコンディショニング、そして何事にも動じない強靭なメンタルという、三位一体の結晶だったのです。
彼の軌跡は、日刊スポーツをはじめとする多くのメディアが報じてきた通り、日本の野球界が長年抱えてきた「投げ込みこそ正義」「苦しまなければ成長はない」という古い価値観への、静かな、しかし最もパワフルな挑戦状と言えるでしょう。
私たち少年野球に関わる大人が、この事実から本当に学ぶべきこと。それは、彼の特殊な技術やトレーニングをそのまま模倣することではありません。
「なぜ、この練習が必要なのか?」
「本当に、子供の成長につながっているのか?」
常にその本質を問い続け、目の前の子供一人ひとりの体と心に真摯に向き合うこと。そして時には、世間の常識に逆らってでも、「やりすぎない、投げさせない勇気」を持つことではないでしょうか。
野球の楽しさを伝え、怪我から守り、健やかな成長をサポートする。その先にこそ、子供たちの無限の可能性が広がっているはずです。

