山田裕貴が野球を辞めた理由とは?元プロ野球選手の父との逸話に学ぶ、子供の夢の応援法
「お父さん、僕、野球を辞めたいんだ…」
もし、愛する息子が真剣な顔でこう切り出してきたら、あなたは何と声をかけますか?
頭ごなしに否定したり、理由を問い詰めたりする前に、少しだけ耳を傾けてみませんか?同じような悩みを抱える野球パパたちの、週末のグラウンドでの立ち話を。きっと、あなただけが悩んでいるのではないと気づけるはずです。
今回の記事のテーマは、今をときめく俳優・山田裕貴さんと、元プロ野球選手である父・和利さんの物語です。
華々しい活躍の裏で、裕貴さんが一度は本気で追いかけた野球の夢を「辞める」という大きな決断をしていたことは、あまり知られていません。そして、その決断の影には、寡黙な父との深く、そして少し切ない親子のドラマがありました。
この記事では、音声での会話の続きとして、山田さん親子に実際に起こったエピソードを深く掘り下げながら、子供が夢を諦めようとしている時に、親としてどう向き合い、どう支えるべきか、その具体的なヒントを探っていきます。
この記事を読み終える頃には、「辞める」という決断が、必ずしも終わりではなく、子供が自分の人生を歩むための「新たな始まり」になり得ることを、きっとご理解いただけるはずです。
俳優・山田裕貴の原点:父・山田和利との野球で結ばれた絆
俳優・山田裕貴を語る上で、父・山田和利さんの存在は欠かせません。父・和利さんは、1983年にドラフト4位で中日ドラゴンズに入団し、その後広島東洋カープでも内野手として活躍。引退後は両球団で長きにわたりコーチを務め、多くの名選手を育て上げた、まさに球界のプロフェッショナルです。
そんな偉大な父の背中を見て育った裕貴さんが、野球に憧れを抱くのはごく自然なことでした。小学4年生の時、テレビの向こうで躍動する父の姿に「うわー、カッケー」と胸を熱くし、「自分もあの舞台に立ちたい」と、自らの意志で白球を追いかける日々をスタートさせました。
父もまた、息子の情熱を静かに見守り、裕貴さんは全国大会の常連である強豪クラブチームに所属。プロ野球選手になるという大きな夢に向かって、練習に明け暮れていました。
親子を繋ぐ「野球」という絆の深さを象徴する出来事が、2018年8月10日にナゴヤドームで行われた始球式です。マウンドに立った裕貴さんが身にまとっていたのは、父が中日在籍時に背負った栄光の背番号「30」。
一球を投じた後、彼は感極まった表情でこう語りました。
「あの頃、父の背中を追いかけていた自分を思い出して、この場所で始球式ができたことに貴重な意味を感じています」
その目には、光るものがありました。野球を辞めてから長い年月が経ってもなお、彼の心の最も深い場所には、尊敬する父と、夢中でボールを追いかけた野球少年だった頃の自分が、確かに存在し続けていたのです。彼のアイデンティティの根幹には、常にこの二つの存在が色濃く焼き付いていました。
「プロ野球選手の息子」という重圧と夢の断念

憧れから始まった野球人生でしたが、中学時代に大きな壁にぶつかります。裕貴さんが所属していたのは、全国レベルの強豪として知られる「名古屋北リトルシニア」。そこは、まるで野球漫画の世界から飛び出してきたような猛者たちが、全国から集まる場所でした。「片手でリンゴを握りつぶすようなヤツらがゴロゴロいた」と本人が語るように、才能と努力がひしめき合う、あまりにも厳しい環境だったのです。
入団当初は上位打線を任されることもありましたが、レベルの高い投手たちを前に、次第に快音は響かなくなり、定位置はベンチへと移っていきました。
しかし、技術的な壁以上に彼を苦しめたのは、目に見えないプレッシャーでした。
「あいつのおやじ、プロ野球選手なのに」
スタンドからの囁き、チームメイトからの視線、そのすべてが、思春期の少年の肩に重くのしかかります。「山田和利の息子」という看板は、いつしか誇りから重荷へと変わっていました。
「ふと我に返った時に、『あれ、これは俺の人生を生きているのか? 父親を追いかけているのか?』って分かんなくなっちゃって…」
自分の意志でバットを振っているのか、それとも「プロの息子」という役割を演じさせられているのか。アイデンティティの葛藤が、彼の心を蝕んでいきました。
そして、夢を諦める決定的な瞬間は、中学3年生の時に訪れます。父・和利さんが観戦に来たある試合で、裕貴さんは投手として完封し、打者としても3安打を放つという、まさに完璧な活躍を見せました。「今日こそは、親父に褒めてもらえるかもしれない」。淡い期待を胸に乗り込んだ、帰りの車中。しかし、父の口から出たのは、労いの言葉ではなく、あまりにも厳しい一言でした。
「まだまだだな」
その一言が、彼の心をポキリと折ってしまいました。「うわぁ…あんなに頑張ったのに、まだまだなんだ…」「俺には無理かもな」。燃え盛る炎に、冷や水を浴びせられたような絶望感。彼はこの時、自ら夢の扉を閉ざしてしまったのです。
高いプライドが邪魔をして、父に「どうすればもっと上手くなれる?」と教えを乞うことはできませんでした。そして父もまた、「プロはアマチュアに教えない」という固い信念を、たとえ息子が相手であろうと曲げませんでした。結果として、二人の間で野球の技術的な会話はほとんど交わされることなく、心の距離は少しずつ離れていきました。
「なぜ続けないんだ」父が本当に問いたかったこと
ついに、裕貴さんは父に「野球を辞める」という決意を伝えます。どんな言葉が返ってくるのか。厳しい叱責か、それとも落胆のため息か。しかし、父の反応は彼の予想を裏切るものでした。
「俺は(野球を)やれ、とは言ってない。何で自分でやると決めたことを最後までやらないんだ」
この言葉を、当時の裕貴さんは「辞めることを責められた」と受け取ったかもしれません。しかし、今改めてこの言葉を紐解くと、そこには和利さんの深い教育哲学が隠されています。
父が問うたのは、野球という”手段”を続けるかどうかではありませんでした。彼が本当に問いたかったのは、一度「やると決めた」ことに対する”姿勢”であり、困難に直面した時にどう向き合うかという”覚悟”だったのです。
「辞める」という選択そのものを否定するのではなく、「なぜ、自分で決めた目標を、自分自身の手で投げ出してしまうのか?」という、より本質的な問いかけでした。それは、子供の人生における「結果」ではなく、その「過程」における心の在り方を問う、親としての深い対話の試みだったのです。
この言葉は、すぐに彼の人生を変えたわけではありません。しかし、この問いかけは、まるで時限爆弾のように彼の心の奥深くに埋め込まれ、数年後、彼の人生を劇的に変えるきっかけとなるのです。この父の言葉こそが、後の山田裕貴の人生哲学である「次にやると決めたことは、死ぬまでやり遂げる」という固い決意の礎となりました。
挫折からの転機:甲園の涙が俳優への道を切り拓いた

野球を辞めた後、裕貴さんは父の母校でもある野球の名門・東邦高校に進学しました。しかし、彼の学生カバンに野球部のバッグが加わることはありませんでした。一度は本気で追いかけた夢に背を向け、彼はどこか目標を見失ったような日々を過ごしていたのかもしれません。
そんな彼の人生に、劇的な転機が訪れます。高校3年生の夏、東邦高校が甲子園への切符を掴んだのです。裕貴さんは、かつてのチームメイトたちを応援するため、アルプススタンドにいました。
照りつける太陽、鳴り響くブラスバンド、地鳴りのような大歓声。その中で、白球を追いかける仲間たちの姿は、眩しいほどに輝いて見えました。試合開始を告げるサイレンが、甲子園の空に響き渡った瞬間、彼の目から涙が止めどなく溢れ出てきました。
「チームメイトはすごい輝いてるし…。僕は野球やめて、自分で人生諦めて、何やってるんだ…」
それは、羨望や嫉妬といった単純な感情ではありませんでした。強烈な後悔の念とともに、あの日の父の言葉が、脳内で鮮明に再生されたのです。
「何で自分でやると決めたことを続けなかったんだ」
その瞬間、彼はすべてを理解しました。父は、野球を辞めたこと自体を責めていたのではなかった。自分で自分の可能性に蓋をして、挑戦から逃げ出した自分の”弱さ”を、父は見抜いていたのだと。スタンドで流した涙は、挫折した過去を洗い流し、新たな未来へと進むための浄化の儀式となりました。
「次にやる、って決めたことは死ぬまでやろう」
そう固く心に誓った彼が見つけた「次にやること」。それが、「俳優」という道でした。父が遠征で家を空けることが多かった少年時代、家族全員がリビングに集まり、一緒に映画やドラマを観ることが、何よりの楽しみだったという原体験が、彼を新たな夢へと導きました。
「家族で見てきた映画やドラマに出る存在になろう」
それは、偉大な父を野球とは違う土俵で「超えられるかもしれない」という挑戦であり、野球で傷ついた「自分の悲しかった心を解き明かす」ための、新たな旅の始まりでもあったのです。
寡黙な父の愛情と、天国からのメッセージ
俳優の道を歩み始めた息子に対し、父・和利さんのスタンスは変わりませんでした。その評価は常に厳しく、そして的確でした。裕貴さんの出演作は必ずチェックし、「もっと凄みを出せ」と表現への要求を突きつけたり、「あの作品はお前の芝居が良いわけじゃなくて、キャラがハマってるだけだからな」と、決して手放しで褒めることはありませんでした。
しかし、その厳しい言葉の裏には、誰よりも息子のことを想う、不器用で深い愛情が隠されていました。その事実は、妹さんの口から、思いがけない形で裕貴さんに伝えられます。
「お父さん、褒める人じゃないけど、『裕貴はよくやっている。俺にはできないことだからすごい』って前にポロッと言ってたよ。映画館に大きく貼り出されているポスターを見て、『大きく名前載ってるね』って、すごく嬉しそうにしてた」
これまで一度も見せたことのなかった父の真意。それを知った裕貴さんは、涙を浮かべながら「…嬉しいです」と、一言絞り出すのがやっとでした。
2025年8月16日、父・和利さんは癌のため、60歳という若さでこの世を去ります。約4年間の長い闘病生活。しかし本人の強い意志で、その事実はごく一部の人間にしか明かされていませんでした。息子に余計な心配をかけたくないという、父としての最後のプライドだったのかもしれません。
亡くなる5日前。裕貴さんは、妻となった西野七瀬さんを伴って名古屋の実家を訪れていました。そこにいたのは、杖をつき、痩せ細ってしまった父の姿。しかしその瞳は、息子夫婦の姿を目に焼き付けるように、ただじっと二人を見つめていたと言います。「最後の顔すんなよ…」と心で叫びながらも、裕貴さんは別れ際に、あえて力強く「またな!」と告げました。
その5日後、容態急変の知らせを受け病院に駆けつけ、家族全員が見守る中、和利さんは静かに旅立ちました。
そして、父の逝去後、生前に収録されていたテレビ番組で、父から裕貴さんへの”最後の手紙”が公開されます。そこに綴られていたのは、これまで裕貴さんがずっと聞きたかったであろう、賞賛の言葉でした。
「あまり褒めたことはありませんが、厳しい世界の中で、戦い抜いているところは、すごいと思います。18歳で東京に行き、どんな苦しい状況であっても諦めずにここまで今日まで、自分の決めた道を続けてきたことに対して、すごいね」
これを聞いた裕貴さんは、「…うれしいですね、改めて」と、父の真意を噛みしめるように、涙ながらに語りました。寡黙な父が天国から届けた言葉は、息子の人生そのものを、何よりも力強く肯定するメッセージとなったのです。
【考察】山田親子の物語から学ぶ「子供の夢」との向き合い方4つの原則
この感動的な親子の物語は、私たちに「子供の夢との向き合い方」について、4つの重要な原則を教えてくれます。
原則1:親は「ドリームキラー」ではなく「ドリームサポーター」であれ
子供が「辞めたい」と言った時、親が一番やってはいけないのは、その夢を頭ごなしに否定する「ドリームキラー」になることです。和利さんは、息子の決断を否定しませんでした。その代わり、「なぜ続けないんだ」と問うことで、子供自身に決断の重さを考えさせました。これは、子供の夢を応援し、自立を促す「ドリームサポーター」としての理想的な姿です。
原則2:結果ではなく「過程」と「覚悟」を問う
和利さんの「まだまだだな」という言葉は、結果への厳しい評価でした。しかし、「なぜ続けないんだ」という問いは、物事に取り組む「過程」と「覚悟」への問いかけです。私たちはつい、子供の試合の勝ち負けやヒットの数といった目に見える「結果」に一喜一憂してしまいます。しかし本当に大切なのは、子供がその目標にどう向き合い、困難をどう乗り越えようとしているか、その過程を認め、励ますことなのです。
原則3:時には「突き放す勇気」が自立を促す
父が野球の技術指導をしなかったことは、一見すると冷たい行為に思えるかもしれません。しかし、結果的にその距離感が、裕貴さんが「父のため」ではなく「自分のため」の人生を探す大きなきっかけとなりました。過保護・過干渉は、時として子供の自立心を奪います。子供が自分の意志で道を選び、自分の足で立ち上がる力を育むためには、親が「突き放す勇気」を持つことも必要なのです。
原則4:一つの夢の終わりを「次への種まき」と捉える
野球という夢が破れた後、裕貴さんが俳優という新たな夢を見つけられたのは、幼い頃の「家族で映画を観た」という楽しい記憶があったからでした。親がすべきことは、一つの夢が終わったことを嘆くのではなく、子供の可能性を信じ、日常生活の中に「次の夢の種」を蒔き続けることです。何気ない会話や、共に過ごす時間の中にこそ、子供の未来を照らすヒントが隠されています。
あなたの子供が「野球、辞めたい」と言い出したら?今すぐできる具体的アクションプラン
では、山田親子の物語から学んだ教訓を、私たちの実生活にどう活かせばよいのでしょうか。もし、あなたの子供が「野球、辞めたい」と言ってきた時に、親として取るべき具体的なアクションを5つのステップにまとめました。
ステップ1:感情的に反応せず、まずは「聞く」に徹する
「もったいない!」「なんで!」という感情的な言葉はぐっとこらえ、まずは子供の気持ちを静かに聞くことに徹しましょう。「そうか、辞めたいと思っているんだね。その気持ち、もう少し詳しく教えてくれるかな?」と、安全な対話の場を作ることが第一歩です。
ステップ2:子供が感じているプレッシャーを特定し、共感する
子供の話の中から、「レギュラーになれないのが辛い」「監督に怒られるのが怖い」「友達関係がうまくいかない」といった、プレッシャーの根源を探りましょう。そして、「そっか、〇〇君と比べられて辛かったんだね」というように、子供の言葉を繰り返しながら、その気持ちに深く共感を示してください。
ステップ3:野球を通して「得られたもの」を一緒に振り返る
辞めることのデメリットを説くのではなく、「野球を始めてから、何か良いことってあったかな?」と、ポジティブな側面を一緒に振り返ってみましょう。「足が速くなったね」「大きな声で挨拶できるようになったね」「〇〇君という最高の仲間ができたじゃないか」など、野球というスポーツを通して得られた、技術以外の価値を再確認させてあげることが大切です。
ステップ4:決断を急かさず「代替案」を提示する
「辞める」か「続ける」かの二者択一である必要はありません。「一度、1ヶ月だけ練習を休んでみる?」「次の大会まで、という目標にしてみない?」など、子供の心の負担を軽くするような代替案をいくつか提示してみましょう。0か100かではない選択肢があることを知るだけで、子供の気持ちは楽になるものです。
ステップ5:最終的な決断は子供に委ね、その選択を全力で肯定する
様々な対話を経た上で、最終的に子供が下した決断がどのようなものであっても、親はそれを全力で肯定してあげてください。「あなたがたくさん悩んで決めたことだから、お父さん(お母さん)はそれを尊重するよ。どんな道に進んでも、私たちはあなたの1番のファンだからね」。この言葉が、子供が次のステップへ踏み出すための、何よりの力になります。
まとめ
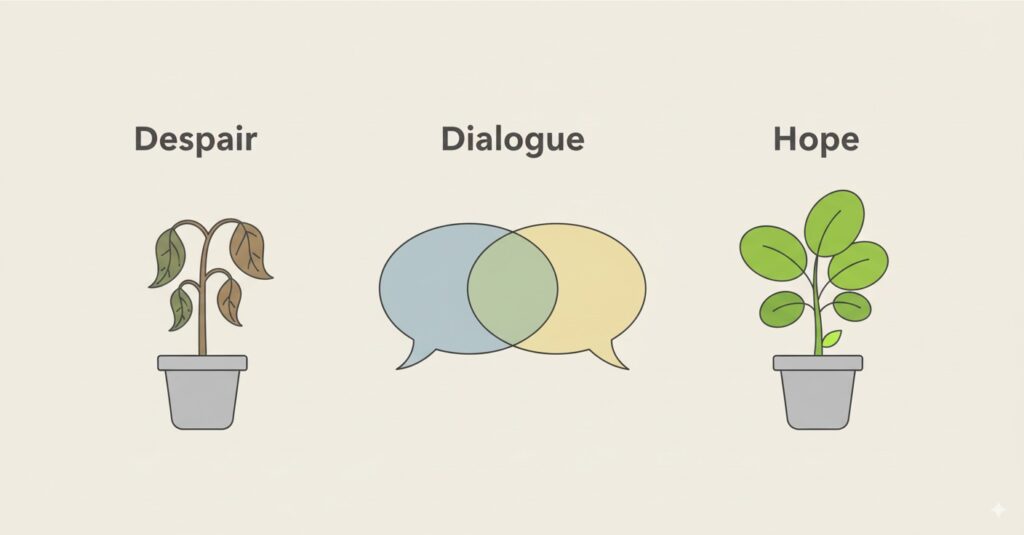
俳優・山田裕貴さんと父・和利さんの物語は、私たちに「続けることだけが正義ではない」という、大切なメッセージを伝えてくれます。
一つの夢を「辞める」という決断は、決して逃げや敗北ではありません。それは、子供が自分自身の人生と真剣に向き合い、自らの意志で未来を選択するための、尊い成長のステップなのです。
親の究極の役割とは、子供の人生のレールを敷くことではなく、子供が自分で道を選び、転んでもまた立ち上がって次の道へ進むための”覚悟”と”エネルギー”を持てるよう、最強の伴走者として、ただ静かに、そして力強くサポートし続けることなのかもしれません。
この記事が、あなたが愛するお子さんと、その夢について深く対話する、一つのきっかけとなることを心から願っています。

