プロに学ぶ「折れない心」。ピンチでこそ輝く!少年野球選手のメンタル強化術
なぜ?試合のプレッシャーに強い子と弱い子の違い
「いけーっ!」「思いっきり振ってこい!」
フェンス越しに声をからして応援するものの、バッターボックスに立つ我が子はガチガチ。練習ではあんなに良いスイングをしているのに、試合になると体が動かなくなってしまう…。
ランナーがたまったり、ピンチになったりすると、急にピッチングが乱れ、フォアボールを連発…。
野球経験のない私(パパ)から見ても、「あぁ、プレッシャーにのまれちゃってるな」と分かるあの瞬間。親として、もどかしく、そして何とかしてあげたいと強く思いますよね。僕も全く同じ気持ちです。
この記事のポイントを、約14分でサクッと耳からインプットできる音声解説も用意しました。 通勤中や家事をしながら「ながら聴き」で概要を掴みたい方は、こちらからどうぞ。
もちろん、文字でじっくりと自分のペースで理解を深めたい方は、このまま読み進めてください。
実は、この「ピンチでの強さ」は、技術だけでは測れない、心の力が大きく影響しています。「野球の9割はメンタルだ」という言葉があるほど、特に少年野球では、子どもの心の状態がプレーに直結するのです。
この記事では、DeNAのルーキー竹田祐投手など、プロ野球選手が見せる「折れない心」をヒントに、私たち親子が普段の生活から実践できるメンタル強化術を、野球ど素人のパパ目線で、具体的かつ分かりやすく解説していきます。
この記事を読み終える頃には、お子さんへの声かけが変わり、親子でプレッシャーを乗り越えるための具体的な武器が手に入っているはずです。一緒に「ピンチを楽しむ心」を育てていきましょう!
プロに学ぶ「折れない心」の正体 ~DeNA竹田祐投手のケーススタディ~

今、プロ野球界で注目を集める一人の若手投手がいます。横浜DeNAベイスターズのドラフト1位ルーキー、竹田祐投手です。彼はプロ初登板から見事2連勝を飾り、その技術もさることながら、特に注目されているのがマウンド上での堂々とした姿と、ピンチでも動じない精神力です。
少年野球の子どもたちにとって、最高の「生きた教材」とも言える竹田投手。彼の強さの秘密は、一体どこにあるのでしょうか。
挫折を乗り越えた経験が「心の土台」に
竹田投手の野球人生は、決してエリート街道ではありませんでした。社会人野球時代には、2度もドラフト指名から漏れるという悔しい経験をしています。一時は自身の投球フォームが「ぐちゃぐちゃ」になってしまうほどのスランプも味わいました。
しかし、彼はそこで腐ることなく、地道な努力を重ねて困難を乗り越えました。この**「思い通りにいかない時期」を経験したことこそが、彼の動じない心の土台**となっているのです。一度どん底を味わったからこそ、少々のピンチでは揺るがない強さを手に入れたと言えるでしょう。
「緊張」を敵ではなく、仲間として受け入れる
多くの選手が「緊張しないように」と考える中、竹田投手のアプローチは少し違います。彼はプロ初登板後、ヒーローインタビューで「すごく緊張したんですけど、いい投球ができてよかった」と、臆することなく自身の緊張を認めました。
これは非常に重要なポイントです。スポーツメンタルトレーニング指導士の筒井香氏も「緊張は、それだけ一生懸命練習してきた本気の証拠」と言います。 緊張を無理に消そうとしたり、緊張する自分をダメだと否定したりするのではなく、「よし、緊張してきたぞ。これは本気のサインだ!」と肯定的に受け入れること。竹田投手は、これを自然に実践しているのです。
ピンチでこそ発揮される「切り替え力」
竹田投手の真骨頂は、ピンチの場面でこそ輝きます。ある試合でプロ初ホームランを浴び、さらに2アウト満塁という絶体絶命のピンチを招いたことがありました。球場の誰もが固唾をのんで見守る中、彼は冷静に次のバッターを打ち取り、見事にピンチを切り抜けたのです。
この驚異的な切り替え力の根底にあるのは、**「過去(打たれたこと)や未来(どうなるか)にとらわれず、今この一球に集中する」**という意識です。
竹田投手の姿は、私たちに教えてくれます。メンタルの強さとは、生まれつきの才能ではなく、経験と正しい考え方によって後天的に身につけられるスキルなのだと。
子供が試合のプレッシャーを「楽しむ」ための思考転換術
プロの考え方が分かったところで、次はそれをどうやって子どもたちに伝え、実践させてあげればいいのでしょうか。ここでは、子どもがプレッシャーを自分の力に変えるための、具体的な思考法の転換術を3つご紹介します。
1. 「緊張は僕のスーパーパワー!」思考
試合前にガチガチになっているお子さんには、こんな風に伝えてみてはどうでしょうか。
「緊張してきた?それ、体が『戦闘準備OK!』って言ってるサインだよ。心臓がドキドキするのは、筋肉にたくさん血液を送って、いつもより速く走ったり、強く投げたりできるように準備してるんだ。緊張は君を強くしてくれるスーパーパワーなんだよ!」
研究によれば、緊張状態は心拍数を上げ、筋肉を活性化させ、集中力を高める効果があることが分かっています。 緊張を「怖いもの」から「自分を強くしてくれる味方」へと意味づけを変えてあげるだけで、子どもの心は驚くほど軽くなります。
ポイントは「緊張を消そうとしない」こと。 「緊張してるなぁ」と客観的に気づき、それを気にせずプレーに集中する。この感覚を親子で共有できると最高です。
2. 「今、このボールだけ」思考
「エラーしたらどうしよう…」「三振したらどうしよう…」
子どもの頭の中は、まだ起こってもいない未来への不安でいっぱいです。この不安こそがプレッシャーの正体。そこで、意識を「今、この瞬間」だけに向けさせる練習が効果的です。
- ピッチャーなら: 「監督のサインとか、次のバッターのこととか、色々考えなくていい。ただ、キャッチャーのミットだけを見て、そこに最高のボールを投げることだけに集中しよう」
- バッターなら: 「ヒットを打とうとか、ランナーを返そうとか、結果は一旦忘れよう。ピッチャーが投げたボールをよく見て、それに合わせてバットを振ることだけに集中だ」
- 守備なら: 「僕のところに飛んでこい!もし来たら、ボールを捕ることだけを考えよう。投げるのは、捕ってから考えればいい」
このように、やるべきことを極限までシンプルにしてあげるのです。子どもが**「自分でコントロールできること(今のプレー)」だけに意識を向ける**手助けをしてあげましょう。
3. 「失敗は最高の作戦会議!」思考
試合での失敗はつきものです。しかし、メンタルが強い子は、失敗の捉え方が違います。彼らにとって、失敗は「終わり」ではなく、「次への始まり」なのです。
三振してベンチに帰ってきた子に、「何で振らないんだ!」と怒るのではなく、「今の球、どう見えた?すごく速かったな。次はもう少しだけ早く準備してみるっていう作戦はどうかな?」と声をかける。
このように、失敗を「次への作戦会議」の材料に変えてあげるのです。 「ピンチは成長の最高のチャンス」という考え方を親子で共有できれば、子どもは失敗を恐れずに、どんどんチャレンジできるようになります。
親子で今日から始める!心を強くする7つの習慣

メンタル強化は、グラウンドの上だけで行うものではありません。実は、日々の家庭での過ごし方や、親子の何気ない会話の中にこそ、子どもの心を強くするヒントが隠されています。ここでは、今日からすぐに実践できる7つの習慣をご紹介します。
習慣1:結果ではなく「過程」を褒める「グッドトライ!」の声かけ
子どもを褒める時、私たちはつい「3安打も打ってすごい!」「完封おめでとう!」と結果に注目してしまいがちです。もちろんそれも大切ですが、心を育てる上では、その結果に至るまでの過程や挑戦する姿勢を具体的に褒めてあげることが何倍も重要になります。
| やってしまいがちなNG声かけ | 心を育てるOK声かけ |
| 「なんでエラーするんだ!」 | 「悔しいな。でも、最後までボールを諦めずに追いかけた姿勢は最高だったぞ!」 |
| 「ヒット打ててよかったな!」 | 「あの厳しいコースの球に、よく食らいついて強くバットを振れたな!すごい集中力だ!」 |
| 「三振か…残念だったな」 | 「結果は三振だったけど、2ストライクからファールで粘ったじゃないか。あの粘りが次につながるよ!」 |
結果は相手や運にも左右されますが、挑戦する姿勢は本人の意思です。そこを認めてあげることで、子どもは「パパは結果だけじゃなく、僕の頑張り自体を見てくれているんだ」と感じ、失敗を恐れない強い心が育ちます。
習慣2:小さな成功体験を積み重ねる「できたこと探し」ゲーム
自己肯定感、つまり「自分はできる!」という感覚は、メンタル強化の土台です。これを育むには、達成可能な小さな目標を立て、それをクリアする経験を積み重ねることが非常に効果的です。
例えば、練習から帰ってきた後に、「今日の練習で、昨日よりちょっとでも上手くできたことは何だった?」と聞いてみるのです。
- 「キャッチボールで、前より少しだけ速い球が捕れるようになった」
- 「素振りで、コーチに言われた通りに腰を回すのを意識できた」
- 「声出しで、一番大きな声を出せた」
どんなに些細なことでも構いません。「できたこと」に光を当てることで、子どもは自分の成長を実感し、自信を深めていきます。
習慣3:マイナス言葉をプラスに変換する「リフレーミング」練習
子どもは「今日の練習、全然ダメだった…」など、ネガティブな言葉を口にすることがあります。そんな時、頭ごなしに「そんなことないよ!」と否定するのではなく、言葉の意味づけ(フレーム)を変える手助けをしてあげましょう。
- 子:「エラーばっかりで最悪だった…」
- 親:「そっか。たくさんエラーしちゃったってことは、それだけボールが飛んできたってことだな!いいポジションにいる証拠じゃないか。次はどうすれば捕れるか、作戦会議しようぜ」
- 子:「緊張して何もできなかった…」
- 親:「それだけ今日の試合が君にとって大事で、本気だったってことだよ。その気持ちが素晴らしい。次は、その本気の力をもっと出せるように、リラックスする方法を試してみようか」
このように、一見ネガティブに見える出来事の「ポジティブな側面」を見つけてあげることで、子どもの自己分析能力や前向きな思考が育まれます。
習慣4:感情を言葉にする「今日の気持ちシェアタイム」
練習後や寝る前など、5分だけでいいので、「今日はどんな気持ちだった?」と子どもの話を聞く時間を作りましょう。
「あの場面、すごく悔しかった」「ホームランを打てて、天にも昇る気持ちだった」「補欠で試合に出られなくて、正直つまらなかった」
大切なのは、どんな感情も否定せずに、ただ「そうか、そう感じたんだな」と受け止めてあげること。 自分の感情を言葉にして誰かに受け止めてもらう経験は、心の安定につながり、自分自身を客観的に見つめる力を養います。
習慣5:魔法の呼吸法「おなかの風船」でリラックス
試合前やピンチの場面で、どうしても緊張が解けない時に即効性があるのが「深呼吸」です。ただ、子どもに「深呼吸しろ」と言っても、やり方が分からないことが多いもの。そこでオススメなのが「おなかの風船」です。
- まず、おへその下あたりに手を当てる。
- 「おなかに風船が入っているのをイメージしてごらん」と声をかける。
- 鼻からゆっくり5秒かけて息を吸いながら、「おなかの風船」を大きく膨らませる。
- 口からゆっくり5秒(もしくはそれ以上)かけて息を吐きながら、「おなかの風船」をしぼませる。
これを試合前やイニングの合間に数回繰り返すだけで、高ぶった神経が落ち着き、心拍数が安定します。お風呂の中や寝る前など、普段から練習しておくと、いざという時に自分でできるようになります。
習慣6:笑顔の力を活用する「スマイル・スイッチ」
2025年の夏の甲子園、絶体絶命のピンチでも笑顔を絶やさなかった日大三・近藤投手の姿を覚えている方も多いでしょう。実は、笑顔には心と体の緊張を科学的にほぐす効果があるのです。
意識的に口角を上げるだけでも、脳は「楽しい」と錯覚し、リラックス効果のあるホルモンを分泌します。ピンチの場面でマウンドに集まった時、「よーし、みんなでニッコリしてみようか!」と声をかけたり、親子で「ピンチになったら、まず笑顔」という合言葉を決めたりするのも面白いかもしれません。
習慣7:「もしも」を想定する「シナリオ・トレーニング」
元プロ野球選手の森本稀哲氏は「平凡な僕がプロで17年もやれた理由はメンタル力」と語っています。 そして、そのメンタルを支えていたのが徹底した「準備」でした。
家庭での会話の中で、「もし、ノーアウト満塁で自分のところにゴロが飛んできたら、まずどこに投げる?」といったシミュレーションをしてみましょう。様々な場面を事前に想定しておくことで、いざその状況になった時に、「あ、これ練習したやつだ!」と慌てずに対処できるようになります。
【新発想】そもそも「メンタルを鍛える」必要はない?
ここまでメンタルを「鍛える」という視点でお話してきましたが、最後に一つ、興味深い考え方をご紹介します。ある全国大会で優勝した少年野球チームの監督は、なんと「メンタルを鍛える必要なんてない」と断言しているのです。
これは一体どういうことでしょうか?
その監督はこう続けます。
「子どもが緊張するのは、準備が足りていないからです。練習で考えられるあらゆる場面を想定し、その対処法を体に染み込ませておく。野球というスポーツを深く理解すれば、想定外のことはほとんど起こらなくなる。想定外がなくなれば、怖さもなくなり、自然と落ち着いてプレーできるんです」
つまり、最高のメンタルトレーニングとは、最高の準備をすることに他ならない、というアプローチです。
技術練習とメンタルトレーニングは、決して別々のものではありません。一つ一つのプレーの目的を理解し、「なぜこの練習が必要なのか」を子ども自身が納得して取り組む。その地道な積み重ねが、揺るぎない自信を生み、結果として「強いメンタル」につながっていくのです。
まとめ
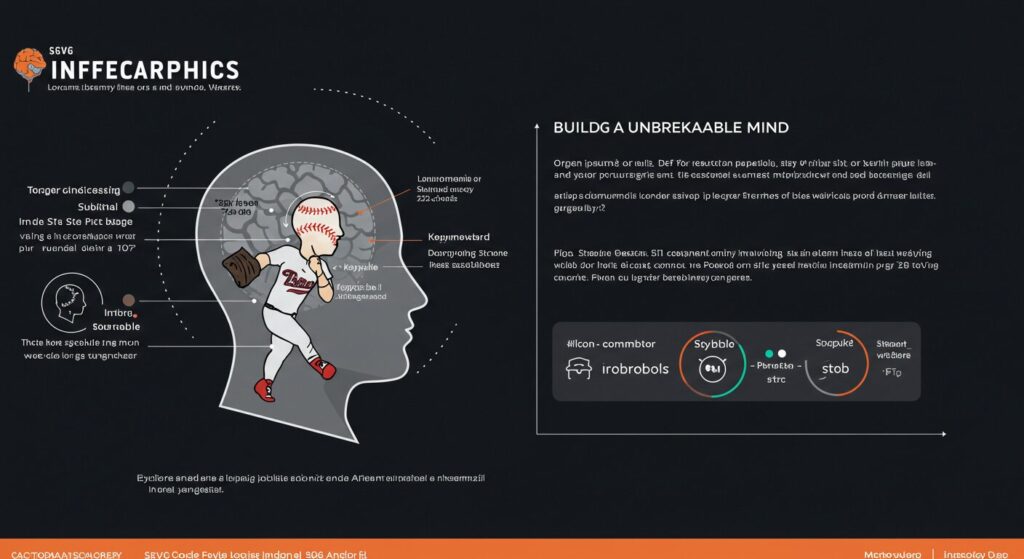
今回は、DeNA竹田投手の姿をヒントに、少年野球におけるメンタルの重要性と、親子で実践できる具体的な強化術についてお話してきました。
最後に、大切なポイントをもう一度振り返ってみましょう。
- プロの強さの源は挫折経験と準備: 竹田投手のように、困難を乗り越えた経験が心の土台を作る。
- 思考の転換がカギ: 「緊張は味方」「今に集中」「失敗はチャンス」という考え方を親子で共有する。
- メンタルは家庭で育つ: 日々の「過程を褒める声かけ」や「小さな成功体験」の積み重ねが、子どもの自己肯定感を育む。
- 最高の準備が最高の自信を生む: 練習で万全の準備をすることが、何よりのメンタルトレーニングになる。
メンタル強化は、一朝一夕で結果が出るものではありません。まるで筋トレのように、日々の小さな積み重ねが、少しずつ、しかし確実に子どもの「心の筋肉」を強くしていきます。
私たち親にできるのは、結果に一喜一憂するのではなく、子どもがプレッシャーと向き合い、失敗から学び、挑戦していくすべてのプロセスを温かく見守り、応援し続けることなのかもしれません。
竹田投手のように、いつか我が子がピンチの場面でこそ輝く姿を見せてくれる日を信じて、今日から一緒に、一歩ずつ歩んでいきませんか。

