なぜファンは阿部監督の「捕手采配」に揺れるのか?
「なぜ、今日も大城じゃないんだ…」
「なぜ、今日も大城じゃないんだ…」
「監督は、大城の価値を分かっていないんじゃないか?」
読売ジャイアンツを心から愛するファンであればあるほど、近年の阿部慎之助監督が執る「捕手併用策」、特にチームの扇の要である大城卓三選手の起用法について、一度ならず疑問やもどかしさを感じたことがあるのではないでしょうか。
打てて、勝てる。2023年のWBCでは侍ジャパンの一員として世界一にも貢献した大城選手。彼がグラウンドにいる時の安心感、投手陣からの信頼の厚さを知っているからこそ、スタメンマスクを他の捕手に譲る試合が続くと、不安や不満が募るのは当然の心理です。
この記事では、そうしたファンの皆さんの感情に寄り添いながら、単なる采配批判ではなく、阿部監督の過去の発言や各種データ、専門家の分析を基に「なぜ、その采配を執るのか?」という”真意”に徹底的に迫ります。
まずは、この記事のテーマについて対談形式でさらに深く掘り下げた以下の音声解説で、議論の全体像を掴んでみてください。 音声で概要をインプットしてから記事を読み進めていただくと、監督の「深謀遠慮」がより立体的に理解できるはずです。
いかがでしたでしょうか。
音声でお話ししたように、一見不可解にも思える采配の裏には、監督自身の経験に裏打ちされた深い戦略が隠されています。
この記事を最後まで読めば、あなたが感じているモヤモヤの正体が明らかになるだけでなく、
- 阿部監督が大城選手に抱く、一見矛盾した「本当の評価」
- 「捕手併用策」という戦術に隠された、緻密な戦略と深謀遠慮
- 今後のジャイアンツの試合を、これまで以上に深く、面白く観るための新たな視点
これらが手に入り、今後の観戦がさらに面白くなること間違いなしです。監督と選手、そしてチームが目指す「勝利」という一点に向かって、今、水面下で何が起きているのか。一緒にその深淵を覗いていきましょう。
【第1の視点】阿部監督は大城卓三をどう評価しているのか?

まず、全ての議論の出発点として、阿部監督が大城選手という一人の捕手をどう評価しているのかを正確に理解する必要があります。監督の発言を紐解くと、そこには「絶大な期待」と「厳しい要求」という、一見すると矛盾した二つの側面が浮かび上がってきます。
「超一流になれる」- 長期的な期待と揺るぎない信頼
一部のファンからは「監督は大城を信頼していないのでは?」という声も聞こえてきますが、公の場での発言を見る限り、その評価の根底には揺るぎない信頼と大きな期待があることが分かります。
監督就任直後の2023年12月、ラジオ番組で監督は「主戦は大城でいきたい」と明言。2023年シーズンの打率.281、16本塁打、そして盗塁阻止率リーグ2位という攻守にわたる実績を高く評価していました。
さらに重要なのは、その期待が単なるレギュラー格にとどまらない点です。監督は「今後10年近く正捕手として、本当の意味で打てるキャッチャーとして定着してほしい」とも語っており、大城選手をチームの長期的な中心選手として明確に位置づけています。
2024年シーズン中にも、「攻守の切り替えがうまくできれば変わってくる。点取られても自分で打って返せばいいんでしょ、くらいの負けん気を持ったり。そういうメンタルで野球できたら大城は超一流のキャッチャーになれる」と、そのポテンシャルの高さを認める発言をしています。
これらの言葉から分かるのは、阿部監督が大城選手の持つ才能、特に「打てる捕手」としての価値を誰よりも高く評価しており、そのポテンシャルが完全に開花することを心から願っている、という事実です。
「現状には物足りない」- 厳しい要求の裏にある愛情と原体験
一方で、阿部監督が大城選手に厳しい言葉を投げかけることも少なくありません。この「厳しさ」こそが、ファンの心を揺さぶる最大の要因でしょう。
2024年シーズン序盤には「大城メインでいきたいんだけど、はっきり言うと精彩を欠いている」と述べ、スタメン起用時の勝率の低さや打撃不振を指摘。同年9月には「精神力の弱さが露呈してる」とまで踏み込み、守備のミス後に一度もスイングしなかった打席を痛烈に批判しました。
なぜ、これほどまでに厳しい言葉をかけるのか。それは、突き放しているからではありません。むしろ逆で、「自分と同じ道を歩ませたくない」「自分を超えてほしい」という、捕手出身監督ならではの特別な愛情の裏返しなのです。
野球評論家の野口寿浩氏は「捕手出身の阿部監督が昨年までの大城卓のリードに満足していなかった」と分析しています。その不満の核心は、リードの組み立て方にありました。阿部監督は大城選手のリードを「外角の変化球を中心にした配球が多い」と見ています。
実はこれ、かつての名将・野村克也氏が、若き日の阿部慎之助選手自身に投げかけた指摘と全く同じなのです。野村氏は言いました。
「バッティングのいいキャッチャーは、投手の真っ直ぐにキレがないと、自分が打席に立ったときに置き換えて『これじゃあ打たれてしまう』と思ってしまう。だから変化球中心の配球で何とかかわそうとする」
阿部監督は、現在の大城選手の姿に、かつて自分が悩み、乗り越えようともがいた若い頃の自分を重ねて見ているのです。「守備と打撃をどう切り離してできるか。自分も若い頃ずっと言われていたけど、なかなかできなかった」という発言は、まさにその心境を物語っています。
だからこそ、二軍降格を命じた際にも「1番のメインは気分転換。素晴らしいものを持っているんだから『野球が楽しいな』とかね。そういった原点に戻ってきてくれ」と、その才能を認めた上での「建設的な指導」であることを強調するのです。
評価のまとめ:期待と課題のアンビバレンス
ここまでを整理すると、阿部監督の大城選手に対する評価は、決して単純な「好き嫌い」や「信頼の有無」で語れるものではないことが分かります。
- 才能への評価: 「打てる捕手」としてのポテンシャルは球界でも屈指であり、「超一流」になれる器だと確信している。
- 現状への評価: 捕手としてのリード、特に精神的な浮き沈みがプレーに影響する点については、まだまだ発展途上であり、大きな課題を抱えている。
この、いわば「愛しているからこそ、許せない」というアンビバレントな(両価的な)感情こそが、阿部監督の評価の核心です。この二律背反の視点を理解することが、次のテーマである「捕手併用策」の真意を読み解く鍵となります。
【第2の視点】なぜ「捕手併用策」を採るのか?その戦術的真意とは

監督が大城選手の才能を信じているのなら、なぜ不動の正捕手として固定しないのか。ここに、ファンが抱く最大の疑問があります。その答えは、阿部監督の野球哲学と、現代野球の特性を理解することで見えてきます。
大前提:「勝利至上主義」と捕手出身監督のDNA
まず理解すべきは、阿部監督が徹底した「勝利至上主義者」であるという点です。そして、その根底には「捕手というポジションが、最もチームの勝敗を左右する」という、自身の経験に裏打ちされた哲学があります。
元巨人コーチの橋上秀樹氏は、阿部監督の采配をこう分析しています。
「キャッチャーとしての信頼度は小林選手の方があると思います。阿部監督には、対戦チームのピッチャーがよくても、自軍のピッチャーがあまり失点をしないだろうと考えた時に、守備にリスクのあるキャッチャーを起用するということはしないでしょう」
これは非常に重要な指摘です。野手出身の監督であれば、打線の繋がりや得点力を重視して「打てる捕手」を優先する傾向があります。しかし、捕手として幾多の修羅場をくぐり抜けてきた阿部監督は、「捕手の仕事は、まずチームを勝たせること(=失点を防ぐこと)」という考え方がDNAに刻み込まれているのです。
だからこそ、試合状況や投手の調子を冷静に見極め、「今は大城の打力よりも、小林の守備力やリードがチームの勝利に貢献する」と判断すれば、迷わず選手を交代させます。それは大城選手への不信ではなく、その試合に勝つための最善手を選択した、という純粋な戦術的判断なのです。
真意①:理想の正捕手が育つまでの「過渡期の戦術」
驚くべきことに、阿部監督自身、現在の「捕手併用策」が理想の形ではないと公言しています。
「去年、日替わりでやってて、それでも勝てたんですけど、やっぱ『僕の理想』とは違う。本来だったら岸田が (スタメンを)掴んで100試合以上出てほしかったし、そのチャンスを掴めなかった。絶対的にはまだほど遠いかなと感じている」
この発言から見えてくるのは、捕手併用策が「積極的な選択」というよりも、「絶対的な司令塔」が確立されるまでの「過渡期における最適解」であるという事実です。監督の理想は、大城選手であれ岸田選手であれ、誰か一人が圧倒的な実力でレギュラーの座を掴み取り、100試合以上マスクを被るチームになること。しかし、現状ではそこまでの選手がいない。だからこそ、併用という形でチーム全体の穴を埋め、勝利を目指しているのです。
真意②:現代野球における「合理的選択」
この「過渡期の戦術」は、同時に現代野球のトレンドに即した極めて合理的な選択でもあります。そのメリットは、大きく3つに分けられます。
- 疲労管理によるパフォーマンス維持:
シーズン143試合を一人で戦い抜く捕手の肉体的・精神的負担は計り知れません。特に夏場以降の疲労は、キャッチングミスや判断力の低下に直結します。出場試合を適切に管理することで、シーズン終盤の勝負どころで各捕手が最高のパフォーマンスを発揮できる状態を維持する狙いがあります。実際に、2024年6月以降、大城選手の出場を月間10試合程度にコントロールしたところ、チームの失点率が改善したというデータもあります。 - 投手との最適なマッチング:
現代野球では、投手も多種多様です。力で押すタイプ、変化球でかわすタイプ、繊細なコントロールが生命線のタイプ。それぞれの投手の持ち味を最大限に引き出す捕手は、必ずしも一人とは限りません。例えば、「菅野智之には経験豊富な小林誠司」「若手投手には気配りのできる岸田行倫」といったように、投手との相性を考慮してバッテリーを組むことで、投手陣全体のパフォーマンスを底上げする効果が期待できます。事実、小林・岸田両選手が起用された期間中、主要投手のクオリティ・スタート(QS)率が向上したというデータも、この戦術の正しさを裏付けています。 - チーム内競争による相乗効果:
「不動のレギュラー」が存在しない状況は、裏を返せば全選手にチャンスがあるということです。大城選手は小林・岸田両選手のリードや守備を、小林・岸田両選手は大城選手の打撃や肩を参考にし、互いに刺激を受け合う。この健全な競争関係が、捕手陣全体のレベルアップに繋がります。「適材適所」の起用は、チームを活性化させる最も有効な手段の一つなのです。
真意③:大城卓三への「生きた学習機会」の提供
そしてもう一つ、見逃してはならないのが、この併用策が大城選手本人にとって最高の「学習機会」になっているという点です。
阿部監督は「岸田とか小林のキャッチャーとしての振る舞いだったりを勉強して欲しい」と明確に語っています。これは、ベンチから他の捕手のリード、投手への声掛け、構え、ジェスチャーといった、スコアブックには現れない「捕手の技術」を客観的に観察させ、自身のプレーにフィードバックさせたいという教育的意図の表れです。
自分が試合に出ている時には決して見えない景色が、ベンチからなら見える。自分が課題とする「精神的な波」を、他の捕手がどうコントロールしているのかを学ぶことができる。併用策は、大城選手が「超一流」へと脱皮するために、避けては通れない試練であり、またとない成長の機会でもあるのです。
【第3の視点】2025年、甲斐拓也の加入がもたらした変化と今後の展望
これまでの考察に、2025年シーズンからという新たな、そして非常に大きな変数が加わりました。FAでホークスから移籍してきた、侍ジャパンの正捕手・甲斐拓也選手の存在です。彼の加入は、巨人の捕手事情をさらに複雑化させ、阿部監督の併用策を新たなフェーズへと移行させました。
捕手勢力図の激変と新たな併用フェーズ
2025年シーズンが開幕すると、阿部監督は開幕から29試合連続で甲斐選手にスタメンマスクを任せるという、これまでとは異なる起用法を見せました。しかし、チーム状態が上向かない中、5月後半からは岸田選手の起用が増え、交流戦では4捕手の日替わり起用という、まさに「超・併用策」とも言える采配を振るっています。
この変化に伴い、大城選手の立ち位置も大きく変わりました。捕手としての出場は激減し、2024年にも見られた一塁手としての起用がメインとなっています。これは、チームの捕手陣に「守備」という最大の強みを持つ甲斐選手が加わったことで、大城選手の価値を「打力」という側面で最大限に活かそうという、監督の新たな戦略的判断の表れと言えるでしょう。
投手陣からの評価が物語る「併用策の正しさ」
ここで非常に興味深い現象が起きています。それは、巨人の投手陣から、相次いで「甲斐以外の捕手」を称賛する声が上がっているという事実です。
- グリフィン投手: 「岸田は素晴らしい捕手で考えも合う」
- 赤星投手: 「やっぱり小林さんのリードはいいです」
これは決して甲斐選手への批判ではありません。むしろ、「投手によって、最も心地よく投げられる捕手は違う」という、阿部監督が実践する併用策の正しさを、投手たち自身が証明していることに他ならないのです。絶対的な「甲斐一強」体制を敷くのではなく、それぞれの投手の感覚や相性を尊重し、最適なバッテリーを組む。この柔軟な采配こそが、投手陣の信頼を勝ち取り、チーム力を最大化させる鍵であることを示唆しています。
大城卓三の新たな役割と「打てる捕手」の真価
では、捕手としての出場機会が減った大城選手は、その価値を失ったのでしょうか?答えは明確に「ノー」です。
彼の役割は「正捕手」から「打線の中核を担う、捕手もできる強打者」へと変化したのです。捕手という重労働から解放されることで、打撃への集中力は増し、その類稀なるバッティングセンスを遺憾なく発揮することが期待されます。
彼自身、一塁守備で岡本和真選手のホームランが出た際には「(一塁手として)続けてよかった」と語っており、チームから与えられた新たな役割を前向きに受け止め、勝利に貢献しようという強い意志が感じられます。
DH制のないセ・リーグにおいて、守備の負担が大きい捕手ポジションにありながら、打線でも中軸を担える大城選手の存在は、相手チームにとって計り知れない脅威です。阿部監督は、甲斐選手の加入というパズルのピースを得たことで、大城選手の価値を再定義し、チームの得点力を最大化する新たな方程式を見つけ出そうとしているのです。
結論:阿部監督の采配は「非情」か、それとも「深謀遠慮」か
ここまで、様々な角度から阿部監督の捕手采配について考察してきました。最後に、私たちの問いに対する結論を導き出しましょう。
一見すると、ファン、特に大城選手を応援するファンにとっては「非情」にも映る采配。しかし、その一つ一つの判断の裏には、緻密に計算された「深謀遠慮」が存在していました。
- 大城卓三への評価は「育成視点」:
監督は大城選手の才能を誰よりも信じているからこそ、現状に満足せず、厳しい要求を課しています。それは、自身が経験した苦悩を乗り越え、「超一流」の捕手へと成長してほしいという、捕手の先輩としての深い愛情の表れです。 - 「捕手併用策」は「勝利至上主義」に基づく戦術:
この采配は、個人の感情ではなく、「どうすればチームが勝てるか」という一点を追求した結果です。疲労管理、投手との相性、チーム内競争の活性化といった、現代野球における合理的な判断に基づいています。 - 目指すは「絶対的な司令塔」の育成とチーム力の最大化:
併用策は、理想の正捕手が育つまでの過渡期の戦術であり、選手たちにとっては最高の学習機会でもあります。甲斐選手の加入により、その戦術はさらに進化し、各選手の価値を最大限に引き出すフェーズへと入りました。
阿部監督の采配を、一試合ごとの結果だけで判断し、一喜一憂するのは簡単です。しかし、その裏にある大きな物語、つまり「勝利」という共通目標に向かって、チームをどう作り上げ、選手をどう育てようとしているのかという「プロセス」に目を向けることで、私たちの野球観戦は、より深く、豊かなものになるのではないでしょうか。
大城卓三選手が、この厳しい環境と監督からの期待という名のプレッシャーを乗り越え、名実ともに「超一流」の扇の要へと成長を遂げるその日を、今は信じて見守りたい。それこそが、ジャイアンツを愛するファンにとっての、最高の楽しみ方なのかもしれません。
まとめ
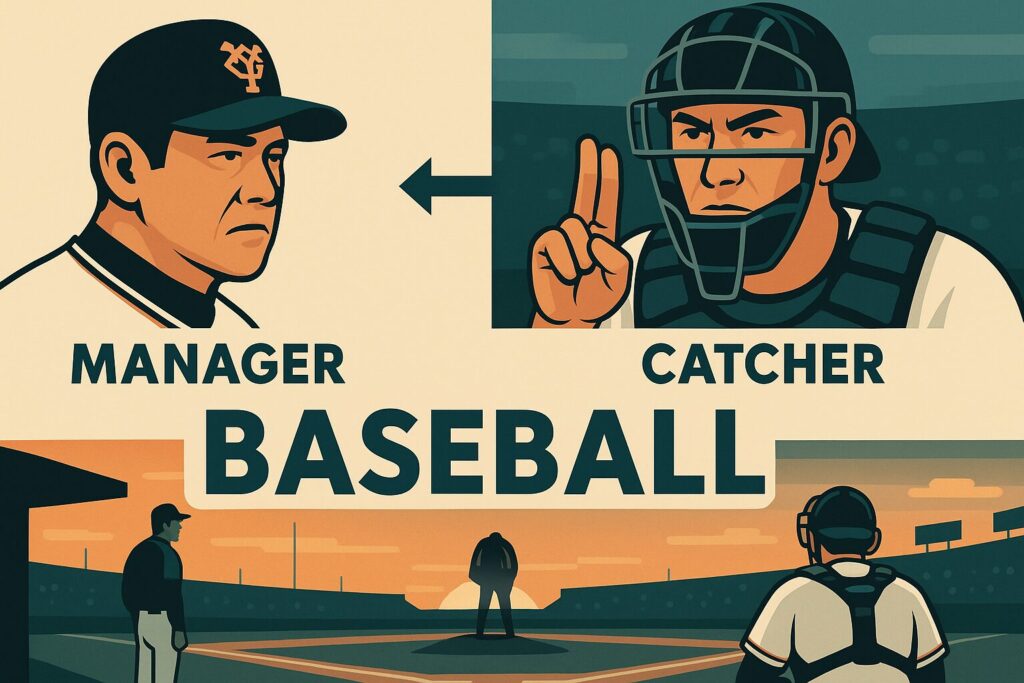
今回は、多くのファンが疑問に思う阿部監督の「捕手併用策」と、大城卓三選手への評価について徹底的に考察しました。
- 阿部監督の大城評: 「超一流になれる」という絶大な期待と、「現状には物足りない」という厳しい要求が同居している。これは成長を願う愛情の裏返しである。
- 捕手併用策の真意: 「勝利至上主義」に基づき、①疲労管理、②投手との相性、③チーム内競争を促す、現代野球における合理的な戦術。
- 併用策の目的: 理想の正捕手が育つまでの「過渡期の戦術」であり、選手にとっては「学習の機会」でもある。
- 甲斐加入後の変化: 大城選手の役割は「打てる捕手」として再定義され、チームの得点力最大化に貢献することが期待されている。
監督の采配の意図を理解すると、一見不可解に見えた選手起用も、勝利への布石として見えてきます。これからは、個々の選手の活躍はもちろん、監督が描くチーム作りの大きなストーリーにも注目して、ジャイアンツの戦いを楽しんでみてはいかがでしょうか。

